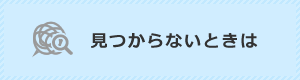今月のおすすめ本
印刷用ページを表示する更新日:2026年2月25日更新
奏でる本
3月19日は、「ミュージックの日」。「3が(ミュー)、19が(ジック)」の語呂合わせから、1991年に日本音楽家ユニオンによって制定されました。これにちなみ、今回は"音"にまつわる本をご紹介します。
1冊目は、河出書房新社『楽器の音色がすぐ聴ける世界の民族楽器図鑑』です。
楽器といえば何を思い浮かべますか?身近なものだとピアノやリコーダー、ギターなどでしょうか。世界には様々な民族によって演奏される多様な民族楽器があり、長く親しまれているからこそ固有文化と密接に関わっています。それぞれ楽器の形状や演奏方法が異なり辿ってきた歴史も多岐に渡るため、楽器の分類は一筋縄ではいかないそうです。本書では、弦が振動する「弦鳴楽器」、空気を吹き込む「気鳴楽器」、膜が振動する「膜鳴楽器」、そして楽器の体そのものが鳴る「体鳴楽器」の四つの仲間に分けて紹介しています。中には、格式高い儀式で演奏される日本の古典音楽「雅楽」に用いる「笙」や「篳篥」なども掲載されています。尚、各楽器の二次元コードを読み取ると実際にその貴重な音色を聴くこともできるので、異国の情景に思いを馳せながら、伝統的な民族楽器の世界に触れてみるのもまた一興です。
2冊目は、エズラ=ジャック=キーツ/さく『ピーターのくちぶえ』です。
ある日、口笛を吹いて犬と遊んでいる男の子を見かけたピーターは、自分も犬のウィリーを口笛で驚かせてみたいと思い、こっそり隠れて試してみますが上手く鳴らすことができません。そこで、転がっていた空き箱の中に隠れたり、お父さんの帽子をかぶり大人になった気持ちで鏡をのぞき込んだりして頬がくたびれるくらい練習しますが、なかなか音は鳴らなくて…。はたして、ピーターは口笛を吹けるようになるのでしょうか。ウィリーを振り向かせようとする一生懸命な姿が微笑ましい絵本です。彼の成長を描いたシリーズとして、他にも『ゆきのひ』や『ピーターのいす』などがあります。ぜひ併せてお楽しみください。
3冊目は、佐原ひかり/著『スターゲイザー』です。
芸能事務所「ユニバース」に所属する透は、アイドルの卵・通称「リトル」の一人。ここでは入所して10年がリトルの寿命とされ、それまでにデビューできなければ自動的に卒業となり、事務所に残留しても舞台やドラマに出演するだけ。つまりアイドルとしてのデビューは絶望的。そんな折、ライブで最も活躍したリトルがデビューするという噂が流れ、最高のパフォーマンスを発揮しようと誰もが歌やダンスに遮二無二励むようになります。「声質」「ビジュアル」「ファンサービス」、どれをとっても互いを羨まずにはいられない感情や胸に秘めた様々な思いが交錯する中、透は若さを費やしすべてを捧げなければデビューが叶わないことに疑問を抱き始めます。そればかりか、シンメトリーで踊る相棒の余命が短いことには深く踏み込めずにいて…。
6編からなる本作は、メインとなる6人のリトルそれぞれの視点で描かれた青春アイドル群像劇で、夢を抱いたことがある人や今推しがいるという人には一層響くものがある物語です。
今回ご紹介した本の他にも、メディア化した音楽小説やクラシック鑑賞の入門書、音楽著作権に関する本などがあります。本を通して、音の放つ魅力を楽しんでみてください。
1冊目は、河出書房新社『楽器の音色がすぐ聴ける世界の民族楽器図鑑』です。
楽器といえば何を思い浮かべますか?身近なものだとピアノやリコーダー、ギターなどでしょうか。世界には様々な民族によって演奏される多様な民族楽器があり、長く親しまれているからこそ固有文化と密接に関わっています。それぞれ楽器の形状や演奏方法が異なり辿ってきた歴史も多岐に渡るため、楽器の分類は一筋縄ではいかないそうです。本書では、弦が振動する「弦鳴楽器」、空気を吹き込む「気鳴楽器」、膜が振動する「膜鳴楽器」、そして楽器の体そのものが鳴る「体鳴楽器」の四つの仲間に分けて紹介しています。中には、格式高い儀式で演奏される日本の古典音楽「雅楽」に用いる「笙」や「篳篥」なども掲載されています。尚、各楽器の二次元コードを読み取ると実際にその貴重な音色を聴くこともできるので、異国の情景に思いを馳せながら、伝統的な民族楽器の世界に触れてみるのもまた一興です。
2冊目は、エズラ=ジャック=キーツ/さく『ピーターのくちぶえ』です。
ある日、口笛を吹いて犬と遊んでいる男の子を見かけたピーターは、自分も犬のウィリーを口笛で驚かせてみたいと思い、こっそり隠れて試してみますが上手く鳴らすことができません。そこで、転がっていた空き箱の中に隠れたり、お父さんの帽子をかぶり大人になった気持ちで鏡をのぞき込んだりして頬がくたびれるくらい練習しますが、なかなか音は鳴らなくて…。はたして、ピーターは口笛を吹けるようになるのでしょうか。ウィリーを振り向かせようとする一生懸命な姿が微笑ましい絵本です。彼の成長を描いたシリーズとして、他にも『ゆきのひ』や『ピーターのいす』などがあります。ぜひ併せてお楽しみください。
3冊目は、佐原ひかり/著『スターゲイザー』です。
芸能事務所「ユニバース」に所属する透は、アイドルの卵・通称「リトル」の一人。ここでは入所して10年がリトルの寿命とされ、それまでにデビューできなければ自動的に卒業となり、事務所に残留しても舞台やドラマに出演するだけ。つまりアイドルとしてのデビューは絶望的。そんな折、ライブで最も活躍したリトルがデビューするという噂が流れ、最高のパフォーマンスを発揮しようと誰もが歌やダンスに遮二無二励むようになります。「声質」「ビジュアル」「ファンサービス」、どれをとっても互いを羨まずにはいられない感情や胸に秘めた様々な思いが交錯する中、透は若さを費やしすべてを捧げなければデビューが叶わないことに疑問を抱き始めます。そればかりか、シンメトリーで踊る相棒の余命が短いことには深く踏み込めずにいて…。
6編からなる本作は、メインとなる6人のリトルそれぞれの視点で描かれた青春アイドル群像劇で、夢を抱いたことがある人や今推しがいるという人には一層響くものがある物語です。
今回ご紹介した本の他にも、メディア化した音楽小説やクラシック鑑賞の入門書、音楽著作権に関する本などがあります。本を通して、音の放つ魅力を楽しんでみてください。
- 『楽器の音色がすぐ聴ける世界の民族楽器図鑑』<外部リンク> (河出書房新社)
- 『ピーターのくちぶえ』<外部リンク> エズラ=ジャック=キーツ/さく(偕成社)
- 『スターゲイザー』<外部リンク> 佐原ひかり/著(集英社)
前回までのおすすめ本
令和8年1月
- 『幸せ招く縁起物』<外部リンク> 本間美加子/著(翔泳社)
- 『だるまのしゅぎょう』<外部リンク> ませぎりえこ/作(偕成社)
- 『一富士茄子牛焦げルギー』<外部リンク> たなかしん/作 絵(BL出版)
令和7年12月
- 『うきわねこ』<外部リンク> 蜂飼耳/ぶん 牧野千穂/え(ブロンズ新社)
- 『ねこのかんづめ』<外部リンク> 北ふうこ/作(学研教育出版)
- 『満月珈琲店の星読み』<外部リンク> 望月麻衣/著(文藝春秋)
令和7年11月
- 『心と体がうるおう肌にやさしい手作り石けん』<外部リンク> 木下和美/著(大泉書店)
- 『〈洗う〉文化史~「きれい」とは何か~』<外部リンク> 国立歴史民俗博物館・花王株式会社/編(吉川弘文館)
- 『さあ、海外旅行で温泉へ行こう~親切ガイド世界の名湯50選~』<外部リンク> 鈴木浩大/著(みらいパブリッシング)
令和7年10月
- 『育ちすぎたタケノコでメンマを作ってみた。~実はよく知らない植物を育てる・採る・食べる~』<外部リンク> 玉置標本/著(家の光協会)
- 『ツキノワグマの掌を食べたい!~猟師飯から本格フレンチまでジビエ探食記~』<外部リンク> 北尾トロ/著(山と渓谷社)
- 『アジア発酵紀行』<外部リンク> 小倉ヒラク/著(文藝春秋)
令和7年9月
- 『にちようびのぼうけん!』<外部リンク> はたこうしろう/作(ほるぷ出版)
- 『こねこのチョコレート』<外部リンク> B.K.ウィルソン/作 大社玲子/絵(こぐま社)
- 『たんじょう会はきょうりゅうをよんで』<外部リンク> 如月かずさ/作(講談社)
令和7年8月
- 『はちみつスイーツ』<外部リンク> 若山曜子/著(家の光協会)
- 『はちみつ』<外部リンク> ふじわらゆみこ/文 いせひでこ/絵(福音館書店)
- 『プーのはちみつとり』<外部リンク> A.A.ミルン/ぶん(岩波書店)
令和7年7月
- 『文にあたる』<外部リンク> 牟田都子/著(亜紀書房)
- 『装丁物語』<外部リンク> 和田誠/著(中央公論新社)
- 『かがくのとものもと 月刊科学絵本「かがくのとも」の50年』<外部リンク> (福音館書店)
令和7年6月
ブラザーフッド・シスターフッド [PDFファイル/137KB]
- 『最後の息子』<外部リンク> 吉田修一/著(文芸春秋)
- 『めぐり逢いサンドイッチ』<外部リンク> 谷瑞恵/著(KADOKAWA)
- 『小野寺の弟・小野寺の姉』<外部リンク> 西田征史/著(泰文堂)
令和7年5月
- 『ぼくのポーポがこいをした』<外部リンク> 村田紗耶香/作 米増由香/絵(岩崎書店)
- 『薬指の標本』<外部リンク> 小川洋子/著(新潮社)
- 『アスク・ミー・ホワイ』<外部リンク> 古市憲寿/著(マガジンハウス)
令和7年4月
- 『1100日間の葛藤~新型コロナ・パンデミック、専門家たちの記録』<外部リンク> 尾身茂/著(日経BP)
- 『コロナの時代を生きるためのファクトチェック』<外部リンク> 立石陽一郎/著(講談社)
- 『私たちの世代は』<外部リンク> 瀬尾まいこ/著(文藝春秋)
令和7年3月
- 『54字の物語』<外部リンク> 氏田雄介/作(PHP研究所)
- 『異世界居酒屋「のぶ」』<外部リンク> 蝉川夏哉/著(宝島社)
- 『火星の人』<外部リンク> アンディ・ウィアー/著(早川書房)