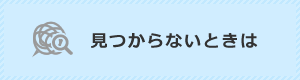所信表明
印刷用ページを表示する更新日:2025年6月12日更新
令和7年6月定例会の開会に際しまして、今後4年間の市政に対する所信の一端を申し述べ、議員各位をはじめ、広く市民の皆様にご理解とご協力をお願い申し上げるものであります。
私は、この度の市長選挙におきまして、無投票での再選を果たすことができましたことは、「坂出再生」に向けて種をまいてきたこれまでの市政運営に対する一定の評価と、今後の市政への期待の表れであると受け止めております。この重責を改めて胸に刻み、次の4年間で花を咲かせられるよう、市民の皆様の負託に応えるべく、全身全霊で市政運営に邁進してまいる所存です。
思い起こせば、市長就任以降、日々鍛えられ、決断力と実行力が試されました。そのような経験のもと、市長という職で大事なことは、変革に挑む覚悟を持つということだと考えております。これまで「坂出再生」のスローガンのもと、変化を恐れず、攻めの姿勢を貫きつつ、足元の課題解決にも積極的に取り組み、議員をはじめ市民の皆様のご協力をいただきながら不断の努力を積み重ねてまいりました。その結果、一定の成果をあげることができたものと自負しております。
特に、最重要施策に位置付けた、坂出駅前および坂出緩衝緑地の再整備につきましては、昨年12月に大林組を中心とした特別目的会社と事業契約を締結し、本年度の駅南口バスターミナルの整備を皮切りとして、北口の駅前広場・駐車場整備、緩衝緑地再整備を順次進め、駅前複合施設の供用を開始する令和10年秋には、市民の皆様にお約束をした新しいまちの姿をお示しすることとなります。「何か、大きなものができる?」、「何か、新しいものができる?」、「何か、素敵なものができる?」、そんなワクワクを創り上げたいと思います。
一方で、1期目においては道半ばの課題や、新たな価値の創造を求められる場面もございました。急加速するデジタル化への取組、カーボンニュートラル社会の実現、不安定な国際社会や円安などを要因とする物価高騰への対応等、直面する課題に対し、市民の皆様の声に真摯に耳を傾け、実効性の高いあらゆる施策を講じていく必要があります。
2期目を迎えるにあたっては、改めて本市の未来を見据え、「坂出再始動、変化する街」の実現に、市民の皆様と共に歩む決意をしております。これまで築き上げてきた礎を継承しながら、時代の変化を捉え、新しい発想で挑戦し、持続可能な自治体をめざすことで、市民の幸せを追求し、市長としてその先頭に立ち坂出の未来を切り拓いていく覚悟でございます。
今後の市政運営にあたり、常に市民の視点に立ち、公正で開かれた市政をめざし未来を創造していくため、次の基本方針を掲げさせていただきました。
まず、災害に強いまちづくりでございます。市民の安全・安心の確保は何よりも優先されるべき市政の最重要課題です。これまでの防災対策に加え、近年頻発する大規模な自然災害の教訓を踏まえ、市民と行政が両輪となって、より一層災害に強いまちづくりを推進してまいります。
具体的には避難所となる体育館の空調整備などのハード対策とあわせ、自主防災組織の育成支援や地区防災計画の策定への市民参加を促進するなど、地域に根ざした防災力の向上を図ります。
また、防災体制をより強化するために、他の自治体と積極的に災害協定を締結し、災害時における応急対策および復旧対策等の相互支援体制を築いてまいります。
次に、農水産業の振興についてでございます。本市の農業・漁業は、地域の経済を支える重要な産業であるにもかかわらず、従事者の高齢化や後継者不足が深刻な課題となっていることから、「6次産業化」を推進し、農業・漁業者の収益増加を図ることにより、新たな担い手や後継者の育成につなげるとともに、「坂出三金時」をはじめとする本市の農水産物ブランドのさらなる流通拡大、販路開拓、消費拡大に向けて積極的にトップセールスを実施してまいります。
次に観光振興でございます。瀬戸大橋の絶景を楽しめる瀬戸大橋記念公園や、沙弥島ナカンダ浜、東山魁夷せとうち美術館、瀬戸内の島々といった既存の観光地の魅力向上を図るとともに、新たな観光ルートや体験型アクティビティの開発を推進してまいります。また、全国区となった「讃岐うどん」や新鮮な魚介類などの食文化について、戦略的なPRに努め、食を目的とした観光客の誘致にも取り組んでまいります。
次に企業誘致でございます。本市が「働きたいまち」としての地位を確立するためには、新たな民間投資を促進することが不可欠であります。坂出北インターチェンジのフルインター化や、さぬき浜街道の4車線化に伴い、本市の地理的優位性が一層高まることを見据えた企業誘致はもとより、さらなる民間投資を呼び込むため、府中湖スマートインターチェンジ等の既存の社会資本をいかした企業誘致に最善を尽くすとともに地域の課題解決に向けた起業支援にも積極的に取り組んでまいります。
次に、子育て支援であります。未来の象徴である子ども達の笑顔が輝き、そのあふれる笑顔が坂出の未来への希望につながります。子育て世代にとって安心して子どもを生み育てられ、安全・安心で質の高い教育環境などの整備は、本市の未来にとって最も重要な投資となります。そのため、令和12年の開校に向け、現在鋭意取り組んでおります学校再編整備については、具体的な協議を進め、子ども達にとって望ましい学校づくりを実現してまいります。また、子育て世代のニーズが多様化するなか、子育て世代が孤立することなく安心して子育てできる環境づくりをめざすとともに、市内各所の都市公園を利用者にとって魅力的な公園に再整備するほか、子育てに関する情報提供の強化など、「このまちで子育てしたい」と心から思えるような環境づくりを推進してまいります。
次に、医療・福祉の充実でございます。まちづくりの重要な要素に「豊かさ」があります。「豊かさ」とは市民の幸福感です。幸福とは「自己肯定」であります。わかりやすく言えば、「誰もが自己肯定感を持てる"まちづくり"」ということです。具体的には、人々の暮らしにゆとりがあり、医療や福祉が行き届いており、市民が健康で、文化や趣味を通じて生きがいを持てる「ウェルビーイング」な環境づくりです。
これらの実現に向け、予防医療の推進や健康増進に関する啓発活動を通じて、高齢者や障がい者、生活困窮者など、誰もが安心して暮らせる医療・福祉を提供してまいります。
次に、脱炭素社会の実現でございます。令和3年9月に「ゼロカーボンシティ」を宣言した本市では、二酸化炭素排出量実質ゼロに向け、公民連携により先進的な施策を展開してまいりました。カーボンニュートラルは、世界的な課題であり、時代の要請であり、カーボンニュートラル社会への迅速な移行を実現するには、公民一体となった取組が鍵となります。これまで以上に市民や事業者などに意識啓発や行動変容を促す取組を進めるとともに、番の州企業とも連携を図りながら、番の州地区の脱炭素化の推進および番の州地区を核とした水素等の次世代エネルギーの利活用を推進してまいります。
次に移住・空き家対策でございます。これまで空き家除却後の土地の固定資産税減免制度の創設など本市独自の対策を講じてきた結果、土地の流動化による新たな民間投資の動きが活発化するなど、効果が顕在化してまいりました。本年度では、旧耐震空き家除却支援制度を創設し、空き家対策を一層加速させたところであり、民間事業者や住宅購入者がまちの価値を選ぶという視点を常に持ち、この新たな動きを一過性で終わらせることなく、中心市街地再生と魅力ある空間の創出につなげてまいります。
一方、移住希望者に対しては、民間事業者と連携しながら空き家を活用した住宅の提供を進めるとともに、移住希望者にとって仕事は移住先を決定する重要な要素であることから、都市部から移住を検討している人材と地元企業のマッチングなども進めてまいります。
最後は、公共交通についてでございます。地域の公共交通は地域社会を持続可能にする基礎的な条件の一つでありますが、人口減少、高齢化、経済縮小によって、維持していくのが困難な状況に陥っており、利用者だけでなく当該地域で暮らす市民全体で支え合うべき「社会的共通資本」でなければ、将来的に維持はできません。
さらに地域交通網を再建するためには、既存の交通手段と新たな交通システムをブレンドし、多様化する選択肢の中で、利便性の向上を図り、機能的に移動システムを創り出していかなければなりません。従って、今後の公共交通の在り方は、多面的な視点から検討が必要となります。そのような中で、近年、全国的に運転手不足が深刻化しており、本市の地域交通網も既存の手段では維持することが困難な状況にあります。これまでの公共交通政策は不足を補填することを軸としてまいりましたが、今後は、現在の運行形態にとらわれない地域の最適な移動手段の確保に向け、新たな交通システムの導入を検討してまいります。
急速な少子高齢化の進行と人口減少、公共施設の老朽化、DXの推進など、立ち向かうべき困難な課題は山積しておりますが、「坂出再始動、変化する街」の実現に向け、全力で取り組んでいく決意を改めて表明いたします。
健康寿命と健康格差の縮小に取り組んでいるなか、高齢者から子どもまで全市民が健康で、「豊かな暮らしを実現するまち坂出」をめざし、今後もさまざまな施策を戦略的・効果的に連動させながら、職員一丸となり、揺るぎない覚悟をもって全身全霊で挑んでまいる所存であります。
何卒、議員各位並びに市民の皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げる次第であります。
私は、この度の市長選挙におきまして、無投票での再選を果たすことができましたことは、「坂出再生」に向けて種をまいてきたこれまでの市政運営に対する一定の評価と、今後の市政への期待の表れであると受け止めております。この重責を改めて胸に刻み、次の4年間で花を咲かせられるよう、市民の皆様の負託に応えるべく、全身全霊で市政運営に邁進してまいる所存です。
思い起こせば、市長就任以降、日々鍛えられ、決断力と実行力が試されました。そのような経験のもと、市長という職で大事なことは、変革に挑む覚悟を持つということだと考えております。これまで「坂出再生」のスローガンのもと、変化を恐れず、攻めの姿勢を貫きつつ、足元の課題解決にも積極的に取り組み、議員をはじめ市民の皆様のご協力をいただきながら不断の努力を積み重ねてまいりました。その結果、一定の成果をあげることができたものと自負しております。
特に、最重要施策に位置付けた、坂出駅前および坂出緩衝緑地の再整備につきましては、昨年12月に大林組を中心とした特別目的会社と事業契約を締結し、本年度の駅南口バスターミナルの整備を皮切りとして、北口の駅前広場・駐車場整備、緩衝緑地再整備を順次進め、駅前複合施設の供用を開始する令和10年秋には、市民の皆様にお約束をした新しいまちの姿をお示しすることとなります。「何か、大きなものができる?」、「何か、新しいものができる?」、「何か、素敵なものができる?」、そんなワクワクを創り上げたいと思います。
一方で、1期目においては道半ばの課題や、新たな価値の創造を求められる場面もございました。急加速するデジタル化への取組、カーボンニュートラル社会の実現、不安定な国際社会や円安などを要因とする物価高騰への対応等、直面する課題に対し、市民の皆様の声に真摯に耳を傾け、実効性の高いあらゆる施策を講じていく必要があります。
2期目を迎えるにあたっては、改めて本市の未来を見据え、「坂出再始動、変化する街」の実現に、市民の皆様と共に歩む決意をしております。これまで築き上げてきた礎を継承しながら、時代の変化を捉え、新しい発想で挑戦し、持続可能な自治体をめざすことで、市民の幸せを追求し、市長としてその先頭に立ち坂出の未来を切り拓いていく覚悟でございます。
今後の市政運営にあたり、常に市民の視点に立ち、公正で開かれた市政をめざし未来を創造していくため、次の基本方針を掲げさせていただきました。
まず、災害に強いまちづくりでございます。市民の安全・安心の確保は何よりも優先されるべき市政の最重要課題です。これまでの防災対策に加え、近年頻発する大規模な自然災害の教訓を踏まえ、市民と行政が両輪となって、より一層災害に強いまちづくりを推進してまいります。
具体的には避難所となる体育館の空調整備などのハード対策とあわせ、自主防災組織の育成支援や地区防災計画の策定への市民参加を促進するなど、地域に根ざした防災力の向上を図ります。
また、防災体制をより強化するために、他の自治体と積極的に災害協定を締結し、災害時における応急対策および復旧対策等の相互支援体制を築いてまいります。
次に、農水産業の振興についてでございます。本市の農業・漁業は、地域の経済を支える重要な産業であるにもかかわらず、従事者の高齢化や後継者不足が深刻な課題となっていることから、「6次産業化」を推進し、農業・漁業者の収益増加を図ることにより、新たな担い手や後継者の育成につなげるとともに、「坂出三金時」をはじめとする本市の農水産物ブランドのさらなる流通拡大、販路開拓、消費拡大に向けて積極的にトップセールスを実施してまいります。
次に観光振興でございます。瀬戸大橋の絶景を楽しめる瀬戸大橋記念公園や、沙弥島ナカンダ浜、東山魁夷せとうち美術館、瀬戸内の島々といった既存の観光地の魅力向上を図るとともに、新たな観光ルートや体験型アクティビティの開発を推進してまいります。また、全国区となった「讃岐うどん」や新鮮な魚介類などの食文化について、戦略的なPRに努め、食を目的とした観光客の誘致にも取り組んでまいります。
次に企業誘致でございます。本市が「働きたいまち」としての地位を確立するためには、新たな民間投資を促進することが不可欠であります。坂出北インターチェンジのフルインター化や、さぬき浜街道の4車線化に伴い、本市の地理的優位性が一層高まることを見据えた企業誘致はもとより、さらなる民間投資を呼び込むため、府中湖スマートインターチェンジ等の既存の社会資本をいかした企業誘致に最善を尽くすとともに地域の課題解決に向けた起業支援にも積極的に取り組んでまいります。
次に、子育て支援であります。未来の象徴である子ども達の笑顔が輝き、そのあふれる笑顔が坂出の未来への希望につながります。子育て世代にとって安心して子どもを生み育てられ、安全・安心で質の高い教育環境などの整備は、本市の未来にとって最も重要な投資となります。そのため、令和12年の開校に向け、現在鋭意取り組んでおります学校再編整備については、具体的な協議を進め、子ども達にとって望ましい学校づくりを実現してまいります。また、子育て世代のニーズが多様化するなか、子育て世代が孤立することなく安心して子育てできる環境づくりをめざすとともに、市内各所の都市公園を利用者にとって魅力的な公園に再整備するほか、子育てに関する情報提供の強化など、「このまちで子育てしたい」と心から思えるような環境づくりを推進してまいります。
次に、医療・福祉の充実でございます。まちづくりの重要な要素に「豊かさ」があります。「豊かさ」とは市民の幸福感です。幸福とは「自己肯定」であります。わかりやすく言えば、「誰もが自己肯定感を持てる"まちづくり"」ということです。具体的には、人々の暮らしにゆとりがあり、医療や福祉が行き届いており、市民が健康で、文化や趣味を通じて生きがいを持てる「ウェルビーイング」な環境づくりです。
これらの実現に向け、予防医療の推進や健康増進に関する啓発活動を通じて、高齢者や障がい者、生活困窮者など、誰もが安心して暮らせる医療・福祉を提供してまいります。
次に、脱炭素社会の実現でございます。令和3年9月に「ゼロカーボンシティ」を宣言した本市では、二酸化炭素排出量実質ゼロに向け、公民連携により先進的な施策を展開してまいりました。カーボンニュートラルは、世界的な課題であり、時代の要請であり、カーボンニュートラル社会への迅速な移行を実現するには、公民一体となった取組が鍵となります。これまで以上に市民や事業者などに意識啓発や行動変容を促す取組を進めるとともに、番の州企業とも連携を図りながら、番の州地区の脱炭素化の推進および番の州地区を核とした水素等の次世代エネルギーの利活用を推進してまいります。
次に移住・空き家対策でございます。これまで空き家除却後の土地の固定資産税減免制度の創設など本市独自の対策を講じてきた結果、土地の流動化による新たな民間投資の動きが活発化するなど、効果が顕在化してまいりました。本年度では、旧耐震空き家除却支援制度を創設し、空き家対策を一層加速させたところであり、民間事業者や住宅購入者がまちの価値を選ぶという視点を常に持ち、この新たな動きを一過性で終わらせることなく、中心市街地再生と魅力ある空間の創出につなげてまいります。
一方、移住希望者に対しては、民間事業者と連携しながら空き家を活用した住宅の提供を進めるとともに、移住希望者にとって仕事は移住先を決定する重要な要素であることから、都市部から移住を検討している人材と地元企業のマッチングなども進めてまいります。
最後は、公共交通についてでございます。地域の公共交通は地域社会を持続可能にする基礎的な条件の一つでありますが、人口減少、高齢化、経済縮小によって、維持していくのが困難な状況に陥っており、利用者だけでなく当該地域で暮らす市民全体で支え合うべき「社会的共通資本」でなければ、将来的に維持はできません。
さらに地域交通網を再建するためには、既存の交通手段と新たな交通システムをブレンドし、多様化する選択肢の中で、利便性の向上を図り、機能的に移動システムを創り出していかなければなりません。従って、今後の公共交通の在り方は、多面的な視点から検討が必要となります。そのような中で、近年、全国的に運転手不足が深刻化しており、本市の地域交通網も既存の手段では維持することが困難な状況にあります。これまでの公共交通政策は不足を補填することを軸としてまいりましたが、今後は、現在の運行形態にとらわれない地域の最適な移動手段の確保に向け、新たな交通システムの導入を検討してまいります。
急速な少子高齢化の進行と人口減少、公共施設の老朽化、DXの推進など、立ち向かうべき困難な課題は山積しておりますが、「坂出再始動、変化する街」の実現に向け、全力で取り組んでいく決意を改めて表明いたします。
健康寿命と健康格差の縮小に取り組んでいるなか、高齢者から子どもまで全市民が健康で、「豊かな暮らしを実現するまち坂出」をめざし、今後もさまざまな施策を戦略的・効果的に連動させながら、職員一丸となり、揺るぎない覚悟をもって全身全霊で挑んでまいる所存であります。
何卒、議員各位並びに市民の皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げる次第であります。