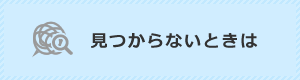施政方針
令和7年3月定例会の開会にあたり、提出いたしました諸議案のご審議をお願いするに先立ちまして、新年度の施政の方針について申し述べたいと存じます。
昨年は令和6年能登半島地震やその被災地を襲った豪雨、日向灘を震源とする地震など、各地で大規模な災害が発生し、自然の脅威を改めて見せつけられました。災害により亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、被災されたすべての方々にお見舞い申し上げます。
能登半島地震に対しては、本市におきましても被災者の健康支援活動の一助を担う保健師の派遣やふるさと納税を活用した代理寄附の受付など、被災地の一日も早い復旧に向けた支援に取り組むと同時に、今後発生が懸念されます南海トラフ巨大地震などの自然災害に備え、災害に強いまちづくりを進めていく決意を新たにいたしました。
昨年夏に開催されましたパリ2024オリンピックでは、競泳男子200メートル平泳ぎに、本市出身の花車優選手が出場し、日本人最高となる5位入賞を果たしました。市役所で行われたパブリックビューイングでは、早朝にもかかわらず多くの市民が集まり、力強い声援を送る姿が印象的であり、ふるさとに夢と希望、そして誇りをもたらしてくれた花車選手に、心より感謝と敬意を表します。
世界に目を向けますと、ロシアによるウクライナ侵攻や中東地域で続く報復の連鎖はいまだ終わりが見えず、相次ぐ異常気象や自然災害による食糧危機の発生など、先行きに不透明感が増しております。また、世界的にインフレが高進するなかで、我が国においても急激に円安が進行し、物価高が暮らしや地域経済を直撃しています。本市においても、引き続き市民の皆さまに寄り添い、迅速かつきめ細やかな支援に意を配してまいります。
ふるさと坂出の再生に向け、明確なビジョンを掲げ、この3年9ヵ月、挑戦を続けてまいりました。振り返りますと、就任当初は、新型コロナウイルス感染症の収束の兆しが見通せないなか、市民の暮らしと生命を守ることを最優先に、円滑なワクチン接種の推進と、コロナ禍において深刻な打撃を受けた暮らしや地域経済の回復に全力を尽くしてまいりました。
このような未曾有の危機に直面するなかでも、坂出再生のために練り上げた公約については、早期実現に向け、努力を積み重ねてまいりました。可能なものから事業展開を図った1年目、組織体制を整え取組を加速させた2年目、市民の皆さまの声や社会情勢の変化を踏まえ熟度を高めた3年目、そして、いよいよ取組の総仕上げを図るとともに、まちづくりが一段と加速する新たな局面を迎えようとしています。
令和10年秋には、坂出駅前の景色が一変します。
最重要施策に位置付け取り組んでまいりました、中心市街地活性化公民連携事業は、昨年8月、これからのまちづくりのパートナーとなる民間事業者を選定し、12月定例会において議会の議決をいただき、事業契約の締結に至りました。公表した事業概要や駅前拠点施設などの完成予想図は、これまでの外部有識者会議やさかいで未来会議、まちづくりアンケートやワークショップなどを通じ、多くの皆さまの参加と対話のプロセスを経て生み出されたものであり、本市のイメージを刷新する、新たなビジョンを示したものであります。
現在、駅前拠点施設などの設計を進めており、新年度には、人を中心とした駅前空間に再編するため、駅南側へのバスターミナル移転に向けた工事等に取り掛かってまいります。
中心市街地再生のためには、空き家問題の解決が欠かせません。
就任当初は、空き家率が県内ワースト1位という看過できない状況にありましたが、空き家除却後の土地の固定資産税減免制度の創設など、先進的に対策を講じてきた結果、商店街エリアなどを中心に空き家の減少が見られ、土地の流動化により新たな民間投資の動きにもつながっております。新年度においては、従来の老朽危険空き家に対する除却支援の受付枠を拡大するほか、旧耐震基準で建築された空き家を対象とした本市独自の除却支援制度を創設することとしており、対策を一層推進してまいります。
国立社会保障・人口問題研究所による将来推計人口によりますと、2050年の本市の人口は3万5千人まで減少するとされており、我が国全体で進行している人口減少は、地域や社会の在り方に大きく関わる問題であり、まさしく「静かな有事」であります。本市では、人口減少対策の指針となる坂出市まち・ひと・しごと創生総合戦略の改定に向けて、先般、パブリックコメントを実施したところであり、基本目標や具体的事業の見直しを図りつつ、市政全般に関わる問題として、施策を総動員して対策に取り組んでまいります。
若者や子育て世代の減少に歯止めをかけ、本市が選ばれるまちとなるためには、生活の基盤となる仕事において、「働きたいまち」として、新たな雇用を創出していく必要があります。企業誘致については、坂出北インターチェンジのフルインター化やさぬき浜街道の4車線化に伴い、本市の地理的優位性が一層高まることを見据え、低未利用地の利活用を促進し、さらなる民間投資を呼び込むため、さぬき浜街道の一部を含む周辺区域の都市計画を見直したところであり、新年度では新たに府中湖スマートインターチェンジをいかした企業誘致に向けて、現行の坂出市都市計画マスタープランについても、改定を進めてまいります。
脱炭素社会の実現と番の州地区を核とした水素等の次世代エネルギーの利活用を推進するため設立した、坂出市番の州コンビナート水素等利活用推進協議会については、調査事業が昨年5月に全国10ヵ所の一つとして国の支援事業に採択され、水素等の利活用に向けた経済、技術、制度面の条件および課題を整理し、水素等の導入による経済的自立の可能性に関する調査を進めてまいりました。新年度においては、公民一体となり、さらに調査内容の掘り下げを進め、個別事案のより専門的な検討を行うと同時に、瀬戸内圏全体を見据えた広域的な連携について協議を深めてまいります。
四国を代表する大型コンビナートである番の州臨海工業団地においては、香川県と連携した企業誘致を進め、現在は重化学工業や流通関係企業など40社を超える企業が立地し、香川県の経済をけん引する役割を担っております。近接する坂出北インターチェンジのフルインター化等により本州と四国を結ぶ優れた物流ネットワークの形成が期待されるなか、四国電力による坂出発電所5号機の建設計画や三菱ケミカル香川事業所のリチウムイオン電池向け負極材の生産能力増強、さらに、先般、発表されたコスモ石油によるSAF製造設備の建設など、新たな民間投資の動きも活発になってきていることから、今後も立地企業と緊密に連携し、工業団地全体の産業競争力、国際競争力の強化に取り組んでまいります。
「働くまち」だが「住むまち」ではないという本市の現状を変えるためには、新たな人の流れを生み出し、にぎわいのある「住みたいまち」を実現していかなければなりません。新年度は2025年大阪・関西万博や瀬戸内国際芸術祭2025などの大型イベントの開催が控えており、これまで以上に瀬戸内地域が注目を集めるまたとない機会となっております。万博では香川県が実施する自治体催事にて、本市の特設ブースを出展する予定であり、瀬戸内国際芸術祭との相乗効果を図りつつ、交流人口の拡大と関係人口の創出に取り組むとともに、昨年12月に着任した移住コーディネーターとも連携して伴走型による相談体制の強化を図り、移住者の受け入れにつなげてまいります。
坂出再生、その未来を担うのは子どもたちです。そして、その未来を創るのは子育て世代であり、若者や女性に選ばれなければ、まちに明るい未来を描くことはできません。
子育て世代への切れ目のない支援に向けては、県内他市町に先駆けて小学校給食費を完全無償化するとともに、子ども医療費助成における18歳までの対象年齢拡大や不妊治療の助成限度額引き上げ、産後ケア事業における利用者負担軽減など、未来を担う「人」への投資を増やしてまいりました。新年度においては、すべての妊産婦、子育て世帯、子どもに対して一体的に相談・支援を行う「こども家庭センター」を新設するほか、保育所等への芸術士の派遣や公園施設のさらなる充実などを計画しており、ハードとソフト両面において、圧倒的に子育てしやすいまちの実現に向けて、全力を尽くしてまいります。
日々変化する時代の潮流に取り残されないためには、スピード感を持って、まちづくりを進めていかなければなりません。私自身、遅れていたまちづくりを前に進めるため、「現状維持は後退でしかない」との強い認識のもと、前例にとらわれることがないよう、常に自問自答を繰り返し、新しい発想で挑戦を続けてまいりました。そして、矢継ぎ早に施策を打ち出していくなかで、職員にも「どうすればできるか」を主体的に考えるよう意識改革を求め、効率的かつ柔軟な市政運営の実現に向けて、市役所一丸となって取り組んでまいりました。
「まちが変わり始めている」という声をいただくようになりました。変化を実感してこそ、将来の暮らしに希望を抱き、まちをより良くしていこうと考えるようになります。そして、変化がもたらすこの「ワクワク感」が人々を惹きつけ、巻き込みながら、まちを再生していくものと確信しております。私はこれからもまちづくりの明確なビジョンを描き、民間の投資意欲を活性化することでまちを動かし、強く明るい坂出を取り戻してまいります。
本市は、恵まれた交通インフラと県下でも有数の企業が立地し、充実した医療・教育環境を有する、中讃地域全体の生活を支えてきたまちであります。先人たちが築いてきたこの繁栄の基盤をさらに強固にし、すべての市民が健康で生きがいを持ち、安全・安心で豊かな暮らしを営むまちをめざして、歩みを進めてまいります。
私は動き出した坂出再生を一歩でも前に進め、市民の幸せを一つでも多く実現できるよう、すべてをかけて市政運営に取り組んでまいる所存であります。議員各位ならびに市民の皆さまのご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
このような方針に基づき編成いたしました新年度予算は、一般会計で
265億2,000万円、特別会計では132億1,151万5千円、企業会計としては、病院事業会計で86億4,198万8千円、下水道事業会計では26億3,414万5千円を計上いたしました。以下、主な事業の概要について、坂出市まちづくり基本構想に示す6つの基本目標に沿ってご説明いたします。
第1の目標は、「すべての人がいきいきと輝くまちづくり」
であります。
中心市街地活性化公民連携事業においては、私の考えるまちづくりの3つの要素である「楽しさ、豊かさ、美しさ」をテーマとして、統一感のあるランドスケープデザインを取り入れ、居心地のよい、歩きたくなるような、ウォーカブルなまちをめざして、現在、検討を進めております。
駅前拠点施設においては、中央に最上階まで貫く4層の吹抜けと施設の顔となる本に囲まれた空間を設けるとともに、各階をスキップフロアとすることで、「坂」の体験と階層間の視覚的なつながりを生み出し、開放的で一体感のある空間を創出してまいります。また、施設は大きく3つの場所に分類され、1階から1.5階は「まちの魅力に出会う場所」としてカフェやコワーキングスペース、地域物産販売所などを配置する、気軽に立ち寄れるにぎわいのある空間、2階から2.5階は「学びに出会う場所」としてライブラリー、多目的活動室などの目的性の高い図書館・交流機能をまとめた空間、3階から3.5階は「こどもの成長に出会う場所」として子育て支援機能やこども図書館、プレイルームなど、親子が安心して過ごせる空間をめざしております。
坂出緩衝緑地エリアにおいては、駅前拠点施設より一足早い令和9年度中の供用開始をめざしており、「明るく心地よい緑」への転換を図るため、コミュニティ拠点施設やカフェを設け、市民が集まり、活動を生み出す場にするとともに、芝生の丘や水辺空間など地形自体が遊び場となる仕掛けを設けることで、子どもの想像力を高める魅力的な空間を創出してまいります。
先般、多くの方にご参加いただき、各エリア整備後の施設の使い方や過ごし方を考えるワークショップを開催し、新たな活用のアイデアをいただいたところであり、今後も多様なまちのプレイヤーと共創し、施設の持つ可能性を最大化できるよう、議論を深めてまいります。
市民との共創によるまちづくりでは、新年度、市政の最上位計画に位置付ける、坂出市まちづくり基本構想の改定を予定しており、先だって、市民生活の満足度や課題等を把握するため、アンケート調査を実施したところです。新年度においてもワークショップの開催を予定しており、これまで以上に市民参加型で、めざすべき将来像について活発な議論を重ね、計画に反映してまいります。
共創によるまちづくりを推進するためには、まちを知ることが重要です。市民の皆さまからも多くのご要望をいただいておりました、広報さかいでの全戸配布について、新年度中の開始に向けて準備を進めてまいります。全戸配布により、市政の現状や行政サービス、イベント情報などをより多くの方に知っていただくことが可能となることから、さらなる市民参画の契機とするため、情報発信の強化に努めてまいります。
多様化する行政需要に対応するため、適切な人材確保に向けて、市職員採用試験の見直しに取り組んでまいります。職員の採用については、年齢制限の引き上げや基礎能力試験の導入などを実施し、社会人経験者等が受験しやすい環境を整備するとともに、人物重視により採用後のミスマッチを減らすため、民間事業者の支援も受けつつ、面接方法等の改善を進めております。新年度においては、応募から採用までを一元管理できる専用のプラットフォームを導入し、手続きのさらなる簡略化と内定者支援の充実に努めてまいります。
行政サービスについては、市民の一層の利便性向上と業務効率化を図るため、フロントヤード改革を推進しており、新年度中に市税をはじめ、介護保険料や保育料・副食費、仲よし教室・みのり教室の利用料などの幅広い分野を対象に口座振替へのオンライン申請を導入し、「書かない・行かない窓口」の実現に取り組んでまいります。
持続可能な都市経営の視点から、業務効率化と並行し、積極的な自主財源の確保に取り組んでおり、ふるさと納税については、2年連続で寄附額が過去最高を更新しております。本年10月には寄附者に対しポイント等を付与するポータルサイトを通じた寄附募集の禁止など、制度の大幅な変更が予定されていることを踏まえ、Amazonふるさと納税の導入等サイトの多角化に努めてまいりました。引き続き市内事業者と連携した返礼品の開発・育成に取り組むとともに、クラウドファンディングや企業版ふるさと納税を推進し、自主財源の確保を進めてまいります。
日本全体で進行する未婚化や出生数の減少に加え、地方においては若年女性が都市部へ流出することで、母親になる女性が地域から減っていく「少母化」が課題となっており、現在の古い性別役割分担意識を改め、女性が子どもを育てながらもいきいきと活躍できる場を増やすとともに、多様な生き方が自由に選択できる、男女共同参画社会の実現が不可欠です。新年度においては、第2次坂出市男女共同参画計画の中間見直しを予定しており、アンケート調査等により現状把握に努め、社会情勢や国の動向なども踏まえ、計画の実効性を高めてまいります。
第2の目標は、「安全で環境に優しく持続可能なまちづくり」
であります。
昨年元日に発生し、今なお多くの方が不自由な生活を余儀なくされている能登半島地震や、8月に発生し、初めて南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表された日向灘地震など、災害の脅威を身近に感じる機会が増えたことに伴い、防災講習や訓練の依頼が増加しており、市民の防災意識の高まりを感じております。
このような現状を踏まえ、新年度においては、地域や家庭における防災力強化に向けて、自治会や自主防災組織と連携し、地形や地域の事情を踏まえた避難所運営マニュアルや地区防災計画の策定に取り組むとともに、豪雨災害の激甚化・頻発化が顕著であることから、これまで浸水想定区域を示せていなかった小規模河川について、新たにハザードマップに反映してまいります。また、災害時等の生活用水を確保するため、市民が所有する井戸を登録する新たな制度を導入することとしており、住民相互の円滑な助け合いにつながるよう「共助」の取組を支援してまいります。
被災者支援の充実については、温暖化の影響により、特に猛暑の時期の大規模災害にあっては、避難所生活が長期化した場合、高齢者等をはじめとするいわゆる災害弱者の二次被害が危惧されることから、新年度より、避難所として指定されている屋内運動場に空調設備を導入してまいります。また、発災後、速やかな生活再建に必要不可欠な罹災証明書については、受付、被害認定、交付までの一連のプロセスをデジタル化し、利便性向上と業務の効率化に取り組んでまいります。
防災行政無線については、長寿命化および機能強化に向けた工事を実施し、災害発生時の迅速かつ的確な情報伝達手段を確保するとともに、さらなる音声品質の向上に努めてまいります。
被害を最小限に抑える減災対策としては、倒壊した住宅が人的被害の拡大や早期復旧の妨げとなった能登半島地震の教訓を踏まえ、新年度より、旧耐震基準の空き家の除却支援制度を創設するほか、申請手続きの煩雑さから、利用者が減少していた家具類の転倒防止対策補助金については、オンライン申請を可能とし、手続きにおける負担軽減を図ってまいります。
地域の安全・安心を守る消防力の強化については、長期使用により老朽化している救助工作車等を新たに整備するとともに、令和8年度に予定する消防ポンプ自動車の更新に向けて、基金を積み立ててまいります。また、こども消防車の再整備については、昨年実施したクラウドファンディングにおいて、多くの皆さまのご支援により、目標金額140万円を達成することができました。改めて感謝申し上げますとともに、ご寄附の趣旨に沿って、有効活用させていただきます。
火葬場は公益性の高い施設であり、安定した稼働が求められます。田尾火葬場については老朽化が著しいことから、火葬炉設備等の延命化を進める一方で、新火葬場整備について、地域住民や関係者の不安や懸念に真摯に向き合い、早期実現に向けて今後も対話を重ねてまいります。
温室効果ガス排出量実質ゼロをめざす「ゼロカーボンシティ」の実現に向けては、さらに多面的な視点から戦略的に施策を展開してまいります。
藻場の再生・創出による海洋生態系の保全とカーボンニュートラルの推進に向けて、昨年2月、香川大学と覚書を締結し、藻場造成の実証事業を開始しております。昨年11月には小与島沖合に藻場造成構造物を沈設したところであり、今後も地元の漁業協同組合等と連携しながら、藻場の繁殖状況の観察を進めるほか、香川大学が実施するリカレントプログラムに参画し、大学との一層の連携強化を図りつつ、施策の深化に努めてまいります。
昨年10月、サントリーグループと協定を締結した「ボトルtoボトル」水平リサイクルについては、新年度より、県内初の取組として事業を開始してまいります。分別収集されたペットボトルを再びペットボトルにリサイクルするこの取組は、化学由来原料からペットボトルを製造する従来の場合と比較してCO2を約60%削減し、ゼロカーボンシティの実現にも寄与することから、先進的に取組を進めてまいります。
ゼロカーボンシティの実現に向けた市民の理解促進と機運醸成を図るため、これまでマイボトル携帯の普及促進に取り組むとともに、EV充電設備について市内18ヵ所に設置を完了したところです。また、令和5年度より3年間の時限措置として創設したZEH基準を満たす住宅取得者への補助制度については、本年度、当初予算額を大きく上回る約60件の申請をいただいております。新年度においても企業版ふるさと納税を活用したセミナーやワークショップ、イベント等の開催準備を進めており、特に次代を担う子どもたちへの興味・関心を高める契機としてまいります。
新年度の新たな施策として、公民連携手法によりJ-クレジットをはじめとする環境価値の創出、流通を推進してまいります。本市においては、これまでにも、環境への配慮、エネルギーコストの削減などを目的に、公共施設についてLED照明への計画的な切り替えを進めてまいりました。一方で、市内全体に目を向けますと同様の取組はもちろん、太陽光発電設備をはじめとする再生可能エネルギーの導入など、脱炭素経営に取り組んでいる民間事業者も増えてきております。これらの取組により生み出される環境価値を埋没させることなく経済価値として循環させる新たな仕組みを導入し、地域のさらなる環境保全に努めてまいります。
第3の目標は、「健康で安心して暮らせるまちづくり」
であります。
人生100年時代、健康であり続けることは万人の願いであり、豊かで生きがいある生活の根幹をなすものです。
坂出市立病院が新築移転し、昨年12月をもって早10年が経過しました。機器や設備を一新し、急性期医療に主軸を置いた医療体制を整備することで悪性疾患等の手術件数が大幅に増加したほか、公立病院として訪問診療やへき地医療を継続し、地域医療の充実にも注力してまいりました。
近年社会問題化している救急搬送の増加については、昨年は過去最高の約2,200件の患者を受け入れ、市民のみならず中讃地域の安全・安心を守るとともに、5類感染症移行後、脅威が去ったかのように見える新型コロナウイルス感染症についても、第二種感染症指定医療機関として、広域から患者の受け入れを継続しており、香川県全域における感染症対策の一翼を担っております。
市立病院は市民の生命と健康を守り、暮らしに安心を与える「頼れる病院」であるとともに、80年近くもの長きにわたり市民が守り抜いてきた「誇れる財産」でもあります。新年度においては、健康で豊かなまちづくりを進めるなかで、その存在意義について、改めて市内外に発信していくとともに、医師の働き方改革や血液内科の機能強化、院内施設の計画的な更新に取り組むこととしており、持続可能な医療提供体制の構築に向けて全力を尽くしてまいります。
健康寿命の延伸や健康格差の縮小に向けては、これまでの健診の受診率向上や生活習慣病予防の取組に加えて、健康に関心がある人に限らず、誰もが自然と健康になれる環境づくりを進めることが重要です。新年度では、香川県のモデル事業として実施している、生活習慣・健康状態見える化事業を拡充し、ウェルネスサポート事業として精力的に取組を進めてまいります。具体的には、引き続きアドバイザーを務める京都大学と連携し、市民の健康づくりについて助言をいただくとともに、これまで乳幼児健診の際に保護者等に実施していた骨密度測定や保健指導等について、子育て支援センターやこども園、学校行事などでも実施し、日々の暮らしの中に健康づくりの要素を取り入れた活動を展開してまいります。
50歳以上の発症率が高く、痛みを伴う水ぶくれが帯状に現れる帯状疱疹については、国がワクチンを定期接種に位置付けたことに伴い、新年度より本市でも自己負担の一部を助成し、接種しやすい体制を整えてまいります。
社会構造の変化により多様化する福祉ニーズのなかで、いわゆる「8050問題」やダブルケアなど、既存制度では対応が困難な複雑化・複合化した課題が顕在化してきております。新年度では、従来の取組をもとに、支援機関等との一層の連携を図りながら、「属性を問わない相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」を一体的に推進する重層的支援体制整備事業を実施し、分野や制度ごとの縦割りを超えた包括的な支援体制の構築をめざして事業を展開してまいります。
子育て支援の充実については、子育て世代に選ばれるまちをめざし、切れ目のない支援策を積極的に講じてまいりました。新年度に向けては、先般、坂出市こども・若者計画に関するパブリックコメントを実施したところであり、新たに設置するこども家庭センターを中心に、取組を加速してまいります。
孤立感や不安感を抱く妊婦等に寄り添った相談支援の実現に向け、子育て支援拠点における面談予約システムの導入や助産師等の専門職の雇用など、支援体制の強化を図るとともに、これまで希望者のみに実施していた面談を、新年度よりすべての妊婦を対象に実施してまいります。また、面談場所もまろっ子ひろばに加えて、京町のわはは・ひろば坂出においても対応できるようにし、2ヵ所体制として利用者の負担軽減に努めてまいります。
さまざまな芸術分野に高い知識を有するアーティストを「芸術士」として、保育所・こども園・幼稚園に派遣する、芸術士派遣事業を実施します。芸術士の派遣により専門性をいかした関わりや助言を行い、絵画や音楽などの表現活動を通じて、子どもたちの自由な発想と感性、創造力を最大限に伸ばしていけるよう取組を進めてまいります。
一人ひとりの人権が尊重される社会の確立に向けた喫緊の課題は、深刻化するインターネットやSNS上での誹謗中傷やプライバシー侵害への対応です。本市では昨年10月に、四国で初めて、インターネット上の誹謗中傷等の防止に関する条例を制定したところであり、新年度からは、被害者等からの相談体制の充実を図るため、弁護士による法律相談を実施することとしており、市民が被害者にも加害者にもならないよう、必要な環境整備を進めてまいります。
第4の目標は、「未来を拓く力をはぐくむまちづくり」
であります。
学校は地域と共にあり、まちづくりに大きな影響を与えるものです。
学校再編整備については、安全・安心で質の高い教育環境の実現を前提とする一方、現在取り組んでおります中心市街地の再生と連動させ、地域の活性化や子育て世代に選ばれるまちづくりにつながるものとして、総合的に検討を進めていく必要があります。
昨年5月に策定した坂出市学校再編整備実施計画では、答申により示された学校再編整備の具体的方策のうち、前期概ね5年程度で整備することとしている再編対象校区について、小中一貫教育の導入や対象校の組合せなど、再編における基本的な考え方をまとめており、現在、当該計画に基づき再編新校(前期)建設基本計画の策定を進めております。その過程では、保護者や地域の皆さまを対象としたアンケート調査やワークショップを実施し、魅力ある学校づくりに資するご意見を数多くいただいているところであり、子どもたちが学び、未来を創造する場所であると同時に、地域の誇りとなり、人々を惹きつける新しい時代の学び舎づくりに向けて、理解と共感が得られるよう今後の方針を示してまいります。
学校教育では確かな学力の育成と、安心して学び、活動できる心の居場所づくりを進めており、教育活動を通して子どもたちが絆を育み、明日も笑顔で通いたくなる学校づくりに取り組んでおります。
多様な教育ニーズの一つであり、喫緊の重要課題である不登校支援については、これまで各中学校に教育支援センターを設置するなど、校内における環境整備を進めるとともに、専任職員と学校が緊密に連携を図りながら、児童生徒の自立に向けた相談や学習サポート等を行ってまいりました。さらに、学校との接点が少ない児童生徒の居場所づくりに向け、本年1月に校外教育支援センターを試験的に開設しており、新年度からは本格運用してまいります。また、小学校段階での不登校児童を支援するため、校内サポートルームの拡充を図ることとしており、安全・安心な居場所とともに、一人ひとりの特性や能力、興味・関心に応じて柔軟に学習ができる環境を整備してまいります。
学校教育を通して、子どもたちが本市の魅力的な地域資源に触れることは、郷土への誇りと愛着を育む貴重な機会となります。令和3年度より小学校において開始したふるさと理解推進事業については、全国有数の産地として本市発展の礎となり、現在も私たちの暮らしと深く結びついている「塩」に関して学ぶ歴史学習や府中湖でのカヌー体験、サヌカイトを使った楽器制作等の本市独自の学習プログラムを実践し、シビックプライドの醸成を図ってまいりました。本年度からは事業を中学校にも拡大し、第2学年での職場体験と関連付けて、バックヤードツアーなども含んだ瀬戸大橋の魅力を直接体感する新たな学習プログラムを開始しており、今後も地域住民や団体、企業と連携し、豊かな体験機会の創出に取り組んでまいります。
市民が健康で心豊かな生活が営めるよう、生涯スポーツ社会の実現をめざして、スポーツに親しめる機会の確保と環境の整備を進めてまいります。府中湖カヌー競技場においては、第1桟橋へのアクセス用スロープの急傾斜が利用者の負担となっており、近年は障がいのある方や子ども、女性の利用も増加していることから、傾斜の緩やかなスロープの整備に向け、新年度では実施設計等に取り組んでまいります。
貴重な文化財の保護・継承は我々の責務であります。新年度では、讃岐国府跡の保存整備に向けた基本計画の策定準備を進める一方、国宝神谷神社においては、災害復旧事業の最終年度を迎え、屋根のふき替えや防災施設の整備を行うこととしており、3年に及んだ事業が完了する見込みです。引き続き文化財の保存に取り組むとともに、その魅力や価値をより多くの人々に伝える仕組みとして、デジタルアーカイブ化を推進し、有効活用を図ることで、地域や観光の振興につなげてまいります。
近年増加し、地域社会や産業の新たな担い手となっている外国人住民については、日本語学習の機会の提供や生活ガイドブックによる情報提供など、安心して生活できる環境整備を進めております。本年度より、国際交流推進マネージャーとして地域おこし協力隊が着任し、関係団体と連携しながら、外国人住民の支援ニーズの調査に取り組んでおります。さらに、地域への参加意識を高め、より多くの外国人住民がコミュニティ活動に関わることができるように、先般、生成AIを活用した多言語による市長メッセージ動画を作成し、ホームページで公開したところです。新年度においては、住環境満足度調査や外国人住民向けのイベントを実施するとともに、一段と分かりやすい情報発信に努め、すべての人が住みやすく暮らしやすい多文化共生社会の実現に向けて効果的に施策を展開してまいります。
第5の目標は、「快適な都市環境を実現できるまちづくり」
であります。
重点的に取組を進めております空き家対策については、先ほども申し上げましたとおり、新年度において補助制度の充実を図り、空き家の除却を一段と促進してまいります。さらに、現行の坂出市空家等対策計画が令和7年度までとなっていることから、改定に向けて、市内全域の空き家について実態把握調査を行うこととしており、今後も「活用の拡大」「管理の確保」「特定空家等の除却」の三本柱で総合的に対策を強化してまいります。
ウォーカブルなまちづくりを進めるうえで要となる市民ホール前広場および周辺整備については、先般、すべての工事が完了し、老朽化した水路等を取り除き、植栽やウッドデッキ、ベンチなどを設置したところであり、駅前通りにふさわしい魅力的な景観と都市のオープンスペースの形成に向けて着実に歩みを進めております。
中心市街地にあり、街なかのオアシスである香風園においては、皆さまからいただいた温かいご寄附を活用して、昨年の観月会にあわせて鯉を再放流することができ、市民に親しまれてきた風景が少しずつよみがえってまいりました。新年度においても池の水質改善を図りながら鯉の放流を継続するとともに、経年劣化が見られる時雨亭の壁土台や階段等を改修し、安全で快適な利用環境を整備してまいります。
坂出再生に向けては、中心市街地活性化公民連携事業の効果を周辺にも広く波及させていく必要があり、郊外から中心部への交通アクセスを確保し、誰もが容易に、利便性を享受できる交通ネットワークを形成していく必要があります。昨年変更した都市計画では、今後、坂出駅周辺の人や車両の流れが大きく変わることを見据え、京町線の道路線形を見直し、駅南側にバスターミナル、北側にタクシー乗り場と自家用車利用ゾーンを配置することにより、これまで京町線が果たしてきた交通結節機能をさらに強化しております。また、福江松山線をはじめとした周辺街路についても、引き続き整備を進め、交通混雑を解消し、車両や歩行者等が安全かつ快適に利用できる都市環境の形成に努めてまいります。また、坂出駅周辺や学園通りにおいては、台風発生時等に道路が冠水し、市民生活に影響を及ぼしていることから、街路整備にあわせて雨水排水管についても整備を行ってまいります。
地域公共交通の維持・活性化に当たっては、全国的にバスの運転手不足が深刻化するなかで、現在の運行形態にとらわれず、地域にとって最適な移動手段の検討を進めることが重要です。先進地域において導入されている自動運転技術については、将来の地域公共交通を担う役割が大きく期待されており、早期に実証実験に取り組むことにより、地域における実現可能性を高めることができるものと考えております。本市でも、新年度における国の補助事業の採択をめざして、実証実験に適した道路条件や日常生活の利便性向上に資する運行ルートなど、幅広い観点より検討を行ってまいります。また、持続可能な公共交通の実現に向けて、引き続き市民の関心を高め、利用促進に取り組むこととしており、「TicketQRで公共交通無料デー」の実施や、本年1月に県内で初めて導入した時刻表や発車情報のほか、地域イベントなどの多様な情報をデジタルで分かりやすく発信する「スマートバス停」を活用した情報発信に努めてまいります。
公園は市民の憩いや健康増進、子どもたちの遊び場をはじめ、余暇活動やコミュニティ活動の場としての機能を有し、良好な都市環境を形成するうえで重要な役割を担っております。公園整備については、計画的に取組を進めており、昨年駐車場を整備し、利便性を高めたことにより利用者が大きく増加した田尾坂公園については、新年度は新たにジェットコースターをモチーフに開発された遊具等を整備するほか、県道33号線から視認できる場所に文字モニュメントを設置することとしており、公園のさらなる魅力化と認知度向上を図ってまいります。
坂出ニューポートプランの策定から5年が経過し、その背景となる市内臨海部の道路ネットワークの整備が進むなど、坂出港の海陸交通における結節点としての重要性が増すなか、新年度では、港湾法に基づく港湾計画の改訂に向けて、環境調査のほか、港湾利用に関するニーズ把握や潜在貨物量の試算等の物流戦略の検討を進めてまいります。また、坂出ニューポートプランに描かれた将来像を実現可能な未来とするためには、坂出港の発展と地域の活性化に向けて、地元企業・団体等との連携が不可欠であることから、四国地方整備局などの関係機関を含め、公民一体となった機運の醸成に努めてまいります。
第6の目標は、「元気とにぎわいのあるまちづくり」
であります。
「四国の玄関口」としての地理的優位性をいかして、本市を軸としたヒト・モノ・カネの新たな流れを生み出し、地域内経済循環に取り組むとともに、暮らしの中ににぎわいのある「住みたいまち」の実現をめざします。
来月13日に、世界中から約2,800万人が訪れる、国際イベントである2025年大阪・関西万博がいよいよ開幕します。香川県においても、会期中に県内の魅力を発信する自治体催事を計画しており、本市もブース出展を予定しております。出展内容としては、世界的にも珍しいサヌカイトが持つ「音」の魅力を通じて、本市を知っていただく機会とするため、風鈴などの展示や販売、ワークショップ等を実施するほか、「坂出」というまちに息づく情景を、音や映像を通して容易に体験できる仕掛けを設けることとしており、外国人を含む新たな関係人口創出の契機としてまいります。
新年度におけるもう一つの大型イベントが瀬戸内国際芸術祭2025です。本市においては、今回も春会期に参加を予定しており、4月18日から5月25日までの38日間、沙弥島と瀬居町、王越町を含む「瀬戸大橋エリア」を舞台に作品が展示されます。今回より始動する瀬居島プロジェクトについては、看板をモチーフにした作品等で注目を集める中崎透氏を中心とした16名の作家が旧瀬居中学校や小学校、幼稚園などの島全体を舞台として作品を展示する大規模なプロジェクトであり、春会期における注目会場の一つとなっております。本市においてもこの好機をいかすため、坂出親子おてつ隊による接待や地域食材をいかした「食」の提供に取り組むとともに、会場内において地元産品の販売を行うなど、同時期に開催される万博との相乗効果を図りつつ、この場所でしか体験できない機会を提供し、訪れる人の満足度を高めてまいります。
万博や芸術祭等を見据えて昨年12月に作成した観光情報誌「るるぶ」の坂出市版については、お出かけスポットやグルメ、お土産、イベント情報等の坂出の魅力を凝縮した一冊として、市外の方にとどまらず、市内の方からも大変ご好評をいただいているところです。大型イベントに備えて既に増刷したところであり、配布先であるサービスエリアや道の駅、空港等にも精力的に働きかけを行い、本市の魅力発信の重要ツールとして活用してまいります。また、効果的な観光情報の提供に向けて、引き続き地域おこし協力隊と連携を図り、新年度は観光PR動画を制作し、広く市内外に発信するとともに、新たな観光資源の開発にも取り組んでまいります。
人口減少による急激な労働市場の変化に伴い、あらゆる産業分野で人手不足が深刻化しており、本市においても昨年10月に香川労働局と協定を締結し、雇用におけるミスマッチ解消や若者の地元定着等に向けて、対策を進めております。参加者ニーズとの乖離が生じていた就職フェアについては、ハローワーク坂出と連携を図り、求人側・求職側ともに求める働き方をより明確にした内容に見直し、今月には、子育て中の方を対象として、仕事との両立が可能な市内の事業所による合同説明会を開催することとしております。
従事者の高齢化や減少により担い手不足が顕著である農業についても、新たな人材確保が喫緊の課題となっております。新年度では、認定を受けた新規就農者に対して、農業用機械の整備等に要した費用を新たに助成するほか、経営が不安定な就農初期段階における資金面での支援に引き続き取り組むなど、人材の確保・育成に向けて幅広く施策を展開してまいります。
安心して農業を営むためには、深刻な農業被害をもたらす有害鳥獣への対策も欠くことができません。鳥獣害防止対策事業におけるイノシシの捕獲状況は近年増加傾向にあり、本年度は過去最多を記録しております。本市としましては、奨励金を増額するなど取組を強化しているところであり、引き続き坂出市猟友会をはじめとする関係機関と協力・連携を図りながら、有害鳥獣への対策に取り組んでまいります。
移住先を選択するのは、就職や結婚、出産などの生活環境が大きく変わるタイミングであり、理想とする暮らしを思い描くなかで、住まいや仕事、生活環境などの情報収集を行い、検討を重ねながら欠かせない要件を整理し、候補となる移住先を選定しております。移住者獲得に向けた自治体間競争が熱を帯びるなかで、本市の現状は、この候補地選定の過程で、移住希望者に必要な情報を届けられていないことが大きな課題であることから、昨年12月に着任した移住コーディネーターを中心に、新年度における本市独自の移住ポータルサイトの立ち上げに向けて、準備を進めております。また、移住フェアなどで活用するパンフレットについても並行して制作を進めており、入口となる情報発信の強化に取り組むとともに、相談や体験機会の充実を図り、移住後の生活環境にも配慮した伴走型の支援体制を構築することで、移住者の増加につなげてまいります。
以上、市政に臨む施策の大綱を申し述べました。
急速な少子高齢化の進行と人口減少、激甚化・頻発化する自然災害、インフラや公共施設の老朽化など、立ち向かうべき困難な課題が山積している今こそ、ためらうことなく決断しなければ、先人たちが築き上げた繁栄の基盤を揺るがし、発展の可能性を閉ざしてしまいます。変化を恐れず、決断と実行により、ふるさとの大いなる発展に挑戦することは、まさに私の本懐とするところであります。
いよいよ坂出再生が本格化します。今後もさまざまな施策を戦略的・効果的に連動させながら、市民が健康で、暮らしのなかに豊かさと生きがいを感じられる、ウェルビーイングなまちを実現するため、不断の努力と不退転の覚悟で市政運営に臨んでまいります。
何とぞ、皆さま方のご理解とご協力、ご支援を賜りますよう心からお願い申し上げ、令和7年度の施政方針といたします。