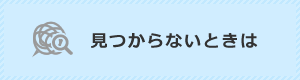国民健康保険税について
国民健康保険税(国保税)の納付は世帯単位で行い,国民健康保険の加入者がいる世帯の世帯主が納税義務者となります。
世帯主のかたが社会保険や後期高齢者医療保険の被保険者で,国民健康保険に加入していなくても,同一世帯内に国民健康保険の加入者がいれば,世帯主のかたが納税義務者となります。このような世帯主のかたを,擬制世帯主といいます。
税額の計算について
坂出市の税率
坂出市の国保税率は以下のとおりです(令和7年4月1日より)。
| 区分 | 対象者 | 所得割額 | 均等割額 | 平等割額 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所得に 応じて計算 |
加入者数に 応じて計算 |
1世帯あたり 共通額 |
|||
| 医療分 | 加入者全員 | 8.8% | 28,000円 | 28,000円 | 66万円 |
| 後期高齢者 支援金分 |
加入者全員 | 2.7% | 8,300円 | 7,000円 | 26万円 |
| 介護分 | 40歳以上 65歳未満 |
2.4% | 9,000円 | 5,500円 | 17万円 |
| 合計 | 13.9% | 45,300円 | 40,500円 | 109万円 | |
所得割額,均等割額,平等割額の合計が年税額になります。
所得割額計算の基礎となる課税標準額
|
課税標準額 = 前年中の所得 - 基礎控除(※43万円) |
|---|
課税の対象となるのは,被保険者の前年中の所得です。複数の所得がある場合は,すべての所得を合計したものが対象となります。所得の計算は下記の表を参照してください。
基礎控除は被保険者それぞれで引きます。市県民税の計算とは異なり,扶養等の控除はありません。
※令和3年度分から基礎控除が43万円に変更になりました。ただし,合計所得金額が2,400万円を超える場合,段階的に減少します。令和2年度分までの基礎控除は33万円です。
| 所得の種類 | 計算式 |
|---|---|
| 給与所得の場合 | 給与収入-給与所得控除-所得金額調整控除 |
| 雑所得(公的年金)の場合 | 年金収入-公的年金等控除 |
| その他所得の場合 | 収入金額-必要経費 |
税額の軽減・減免について
後期高齢者医療制度への移行に伴う緩和措置
措置1:旧国保被保険者がいる世帯における軽減
(国保被保険者であったかたが,後期高齢者医療制度へ移行する場合)
- 法定軽減を受けている世帯は,世帯構成や収入が変わらなければ引き続き同じ軽減を受けられます。
- 国保に加入しているかたが1人になる世帯は,医療分および後期高齢者支援金分の平等割額が5年間半額になります。5年間が経過した場合は,軽減割合を4分の1に縮小した上で,3年間軽減が延長されます。
措置2:旧被扶養者における減免
(被用者保険から後期高齢者医療制度へ移行し,扶養されていたかたが国保加入した場合)
- 所得割額が免除され,資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り,均等割額が半額になります。
- 扶養されていたかた(65歳~74歳)のみで構成される世帯であれば,資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り,上記に加え平等割額も半額になります。
※ただし,法定軽減(7割・5割)の対象世帯については,所得割額の免除のみとなります。
非自発的失業者のかたの軽減措置
対象者(下記の3点の条件すべてに該当するかた)
- 平成21年3月31日以降に離職されたかた
- 離職時点で65歳未満のかた
- 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の「離職理由コード(2桁の数字)」が以下のかた
離職理由 11 12 21 22 23 31 32 33 34
軽減内容
給与所得を30%にして国保税を算定します。原則,離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度まで軽減されます。
この軽減を受けるためには原則申請が必要です。申請に必要なものはマイナンバーカードまたは通知カード,雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(原本)です。なお,通知カードの場合は身分証明書も併せてご持参ください。
子育て世帯への軽減措置
令和4年度分から未就学児の被保険者均等割額が5割軽減されます。
産前産後期間の軽減措置
令和5年11月以降に出産(予定)日を迎えられるかたを対象に軽減措置が行われます。
この軽減を受けるためには原則申請が必要です。詳細は,「産前産後期間国民健康保険税の軽減について」をご覧ください。
法定軽減
所得の少ない世帯の負担を軽くするため,一定基準以下の世帯に対し,均等割額と平等割額が軽減される制度(7割・5割・2割)があります。
※上記の各軽減措置における詳しい内容,申請方法等につきましては,税務課市民税係までお問い合わせください。
納付方法と納期限
- 普通徴収(納付書納付または口座振替):口座振替なら納付の手間がなく便利です。
7月から2月まで(各月の月末が納期限)の年8回での納付になります。
- 特別徴収(年金天引):年金支給日にあらかじめ国保税が天引きされます。
4・6・8月の3回(仮徴収)と10・12・2月の3回(本徴収)の年6回になります。直接窓口で納付する必要はありません。
注意)前年度が年金からの天引きになっているかたでも,所得や世帯構成(当年度中に世帯主が後期高齢者医療保険に移行するなど)によって翌年度の納付方法が変更になる場合があります。詳しくは,7月にお送りする納税通知書をご確認ください。