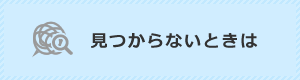固定資産税(家屋)
1.課税対象となる家屋について
地方税法第341条第3号によると、家屋とは、「住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。」とあります。また、不動産登記規則第111条では、「建物は,屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し,土地に定着した建造物であって,その目的とする用途に供し得る状態にあるもの」とあります。
そこで、固定資産税の課税対象となる家屋とは、賦課期日(毎年1月1日)において土地に定着して建造され、屋根および周壁またはこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎ得る一定の空間を有する住家(居宅)、店舗、工場、倉庫、その他の建物のこととされています。
以上より、次の3要件を有するものを課税対象となる家屋と判断します。
(1)定着性
土地に定着しており、基礎があるものをいいます。
(2)遮風性
「屋根」があり、「三方以上の周壁」があるものをいいます。
(3)用途性
建物として使用できる完成状態にあるものをいいます。
よくあるご質問として、「面積の小さい家屋には固定資産税がかからないのではないか?」というものがあります。建築基準法第6条第2項において「(建築確認申請の提出義務に関して)…床面積の合計が10平方メートル以内であるときについては、適用しない」とありますが、地方税法において課税対象となる家屋の面積要件についての記載はありません。よって、坂出市においても地方税法に則って課税しておりますので、課税対象家屋の面積要件はありません。
また、柱と屋根だけのカーポートなどについては、自家用である場合には、固定資産税(家屋)の課税対象にはなりません。ただし、事務所や店舗の来客用等に設置されたカーポートについては「償却資産」として、固定資産税の課税対象になります。
ホームセンター等で売っている物置は、土地への「定着性」が問題となります。基礎があり固定措置が取られている場合は、固定資産税(家屋)の課税対象になります。一方、コンクリートブロックの上や地面の上に置いただけのものについては、土地への定着性がないため、固定資産税(家屋)の課税対象にはなりません。
2.家屋の評価計算について
固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて算出しています。また評価基準では、再建築費(価格)を基準として評価する方法(再建築価格方式)により家屋の評価額を求める方法を採用しています。
新増築の家屋が完成した場合、税務課資産税係の職員(固定資産評価補助員)が訪問し、仕上げの材料や状態、間取り等を調査します。対象となる家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合の建築費を固定資産評価基準の点数で計算します。これを「再建築費評点数」といいます。
そして、この再建築評点数に 家屋建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価を考慮し、その家屋の評価額を求めます。
これを算式で示すと、次のとおりです。
(算式)
家屋の評価額(円)=単位当たり再建築費評点(点/平方メートル)×経年状況による減点補正率
(×需給事情による減点補正率)×床面積(平方メートル)×評点一点当たりの価額(円/点)
「家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜか」というご質問があります。建築物価の変動による建築費の上昇の割合が、年数の経過によって生じる損耗の状況による減価の割合を上回る場合は、前年度よりも評価額が上昇することになっています。しかし、家屋は一般的には減耗資産であり、前年度の評価額を上回ることは望ましくないので、その場合は前年度の評価額に据え置くこととなっています。したがって家屋の評価額は上記の算式にて求められた評価額が、前年度の評価額を下回る場合にのみ下落することになります。
3.新築住宅に対する固定資産税の減額措置について
令和8年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税(家屋)が減額されます。新築住宅にかかる減額措置の適用関係は、以下のとおりです。
該当要件(ア、イ両方を満たすものについて表のとおり)
(ア) 専用住宅や併用住宅(居宅部分の割合が2分の1以上に限る)であること。
(イ) 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(マンションなどでは、独立に区画された部分の面積が40平方メートル以上)
また、認定長期優良住宅(※)については、通常の新築住宅よりも減額期間が拡充されています(下記表参照)。ただし、認定長期優良住宅としての固定資産税の減額適用を受けるためには、認定証(県住宅課)および認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書(様式第36号の14) [PDFファイル/92KB]の提出が必要です。
※長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日(平成21年6月4日)以後に新築されたもの。また、同法の規定に基づき、耐久性や安全性などの住宅性能が一定基準を満たすものとして行政庁の認定を受けて新築された住宅であるもの。
| 区分 | 期間 | 減額される範囲(居住部分のみ) |
|---|---|---|
| 一般住宅 | 3ヶ年 (5ヶ年) |
○床面積が120平方メートル以下の場合 ○床面積が120平方メートル以上280平方メートル以下の場合 |
| 3階建以上の中高層耐火住宅 | 5ヶ年 (7ヶ年) |
※期間の括弧内は認定長期優良住宅の場合。なお、坂出市へ申告書等の提出が必要です。
4.その他の住宅に対する固定資産税の減額措置について
下記に該当する改修を実施した住宅に関しては、一定期間の固定資産税(家屋)が減額されます。減額措置の内容は、以下のとおりです。
(1)耐震改修
該当要件
(ア)令和8年3月31日までの改修であること。
(イ)改修対象家屋が昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること。
(ウ)建築基準法に基づく耐震基準に適合した改修であること。
(エ)改修費用が50万円超の工事であること。
減額の適用期間
改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税1年度分
(通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅は2年度分)
減額される範囲
改修住宅1戸あたり120平方メートル相当分まで2分の1を減額(改修により長期優良住宅に認定された場合は、3分の2を減額)
必要書類
(a)耐震改修工事代金領収書(写し)
(b)増改築等工事証明書
(c)住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書(様式第36号の11) [PDFファイル/83KB]
(d)耐震改修工事後の建物平面図
(e)長期優良住宅に認定されている場合は、認定長期優良住宅であることを証する証明書(写し)
改修工事が完了した日から3か月以内に申請してください。
(2)バリアフリー改修
該当要件
(ア)令和8年3月31日までの改修であること。
(イ)改修対象家屋が新築された日から10年以上を経過した住宅(改修後の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下。)(賃貸住宅は除く。)で、下記の1~3のいずれかに該当するかたが居住であること。
- 65歳以上のかたが居住している住宅であること。
- 要介護認定または要支援認定を受けているかたが居住している住宅であること。
- 障がい者認定を受けているかたが居住している住宅であること。
(ウ)その改修に対する補助金などを除く自己負担額が50万円超の工事(※)であること。
※工事の内容:廊下の改修、階段の勾配の緩和、浴室の改良、便所の改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止め化など
(エ)当該住宅の居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること。
減額の適用期間
改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税1年度分
減額される範囲
改修住宅1戸あたり100平方メートル相当分までの居住部分の3分の1を減額
必要書類
(a)要介護認定または要支援認定を受けているかたは介護保険被保険者証の写し、障がい者のかたは障害者手帳等の写し
(b)次のア、イのいずれか
ア 工事代金領収書(写し)、改修工事の内容と費用の確認できる明細書(写し)および写真(工事前後)
イ 建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する改修工事が行われたことを証する書類
(c)改修工事を行った箇所がわかる建物平面図
(d)改修工事の費用に補助金等の交付を受けている場合は、補助金等の交付決定の写し、居宅介護住宅改修費の給付決定または介護予防住宅改修費の給付決定を受けたことを確認できる書類
(e)住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書(様式第36号の12) [PDFファイル/108KB]
改修工事が完了した日から3か月以内に申請してください。
(3)省エネ改修
該当要件
(ア)令和8年3月31日までの改修であること。
(イ)改修対象家屋が平成26年4月1日以前に建てられた住宅(改修後の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下。)であること。
(ウ)下記1~4の改修工事により、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することになった住宅であること。
- 窓の断熱改修工事(窓の二重サッシ化など)
- 床の断熱改修工事(1と併せて行なうことが必須)
- 天井の断熱改修工事(1と併せて行なうことが必須)
- 壁の断熱改修工事(1と併せて行なうことが必須)
(エ)その改修に対する補助金などを除く自己負担額が60万円超の工事であること。
(オ)当該住宅の居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること。
減額の適用期間
改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税1年度分
減額される範囲
改修住宅1戸あたり120平方メートル相当分まで3分の1を減額(改修により長期優良住宅に認定された場合は、3分の2を減額)
必要書類
(a)建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する改修工事が行われたことを証する書類
(b)改修工事に要した費用を証する書類(写し)
(c)費用に補助金等の交付を受けている場合は、補助金等の交付決定の写し
(d)長期優良住宅に認定されている場合は、認定長期優良住宅であることを証する証明書(写し)
(e)改修工事後の建物平面図
(f)住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書(様式第36号の13) [PDFファイル/98KB]
(注意)現在、新築住宅に係る軽減措置または耐震改修に伴う減額措置等(バリアフリー改修を除く。)の適用を受けているかたは、この減額措置の適用を受けることはできません。
改修工事が完了した日から3か月以内に申請してください。