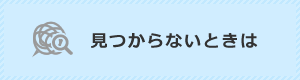マダニ等に咬まれないように注意しよう
ダニが媒介する感染症の中でも、主に「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」、「日本紅斑熱」、「ツツガムシ病」が報告されています。
ダニは、日本中どこにでもおり、レジャーや農作業などで野山や草むら、畑などに入る場合は注意が必要です。春から秋にかけて、活動が活発になることから、ダニに咬まれる危険性が高まります。
ダニ媒体感染症とは
病原体を保有するダニに咬まれることで発症する感染症のことをいいます。
| 感染症名 | 原因のダニ等 | 潜伏期間 | 症状 |
|---|---|---|---|
| 重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | マダニ | 6日から14日 |
発熱、食欲低下、嘔気、嘔吐、腹痛、全身倦怠感など。 高齢者での発症例・重症化例が多くみられる。重症化すると死亡することもある。 |
| 日本紅班熱 | リッチケアや細菌など病原体を保有するマダニ | 2日から8日 | 発熱、発疹、頭痛、全身倦怠感など。 |
| ツツガムシ病 | ツツガムシ | 5日から14日 | 発熱、発疹、赤黒く盛り上がったかさぶた(刺し口)など。 |
予防方法
(1)野外では肌の露出をできるだけ少なくする
長袖・長ズボンが基本です。手袋や長靴にし、袖口を手袋の中に、ズボンを靴の中に入れるようにしましょう。
帽子を被り、首元もタオルを巻くなどして露出しないようにしましょう。
(2)虫よけスプレーを使用する
「ディート」や「イカリジン」の成分を含む虫よけスプレーを使用すると、マダニに付着数が減少します。
効果時間は6から8時間なので、1日のうち何回か使用する必要があります。
(3)ダニを家に持ち込ませない
家に帰ってきた際は、上着や作業服は家の中に持ち込まず、早くにシャワーや入浴で体を洗い流すことも有効です。
咬まれた時の対応
見つけたら早めに取り除くことが重要ですが、無理に引き抜こうとするとダニをつぶし病原体が体内に入ってしまったり、ダニの一部が皮膚内に残って化膿する恐れがあります。自分でつぶしたり、取り除いたりせずに、医療機関で処置してもらいましょう。
また、咬まれたあとしばらくして(数日から2週間程度)、発熱等の症状が認められた場合は医療機関で診察を受けてください。
関連リンク
・ダニ媒介感染症
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164495.html<外部リンク>
・重症熱性血小板減少症候群(Sfts)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000169522.html<外部リンク>