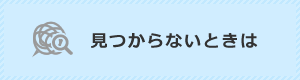保険証とマイナンバーカードについてのお知らせ
保険証とマイナンバーカードが一体化されます
国から示されたマイナンバーカードと保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日以降、現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用)を基本とする仕組みに移行します。令和6年12月2日時点でお手元にある有効な保険証は、券面に記載されている有効期限までは使用することができますが、記載事項(氏名、住所等)に変更が生じた場合は有効期限を待たずに変更日から使用できなくなります。マイナンバーカードを保険証として利用するために、お早めに事前登録をお願いします。詳しくは下記「マイナンバーカードの保険証としての利用について」をご覧ください。
マイナ保険証を保有していないかたへ
令和6年12月2日以降、マイナンバーカードを取得していないかたやマイナンバーカードの保険証利用登録を行っていないかたには、有効期限が切れるタイミングで「資格確認書」を送付します。「資格確認書」を提示することで、引き続き医療機関を受診することができます。また、マイナンバーカードを紛失・更新中のかた、その他特別な事情があるかたには申請により資格確認書を交付します。
上記のとおり、資格確認書の交付には、マイナンバーカードの保有状況等によって、申請が必要な場合と申請が不要な場合があります。国民健康保険資格確認書交付手続きナビ<外部リンク>にご回答いただくことで、申請の要否についてご回答いたしますのでご活用ください。
マイナンバーカードの保険証としての利用について
医療機関や薬局の窓口において、事前登録を行えば、マイナンバーカードを保険証として利用できるようになります。
なお、オンライン資格確認を導入していない医療機関や薬局ではご利用いただけません。事前に厚生労働省ホームページ(全国版<外部リンク>、都道府県別<外部リンク>)でご確認ください。
※マイナンバーカードを保険証として利用できるように登録した場合でも、市役所への国民健康保険の加入・喪失の届出は、これまでどおり必要です。
事前登録の方法
マイナンバーカードを保険証として利用するには、事前登録が必要です。登録については、次のものをご用意のうえ、(マイナポータルサイト<外部リンク>)から手続きしてください。
登録に必要なもの
-
マイナンバーカード
-
マイナンバーカード取得時に設定した利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)
-
スマートフォン(マイナンバー読取対応機種)またはパソコンとICカードリーダー(家族など本人以外のスマートフォンやパソコンでも可)
スマートフォンやパソコンを利用できないときの登録方法について
スマートフォンやパソコンなどをお持ちでない場合は、セブン銀行ATMで申し込みできます(セブン銀行ATMでの健康保険証利用の申し込み<外部リンク>)。
また、市役所本庁舎1階けんこう課窓口でも保険証利用の申し込み支援を行っています。上記の「登録に必要なもの」の1と2をご準備ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
1.保険証としてずっと使える!
マイナンバーカードを使えば、医療保険者で手続済であれば、就職や転職、引越ししても、保険証の発行を待たずに受診できます。
※医療保険者への加入・喪失の届出は引き続き必要です。
2.医療保険の資格確認がスピーディーに!
カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。
3.手続きなしで限度額以上の一時的な支払が不要に!
限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払が免除されます(1医療機関ごとで限度額が適用)。
※自治体独自の医療費助成等については証類の持参が必要です。
4.健康管理や医療の質が向上!
マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。
また、本人が同意をすれば、初めての医療機関等でも、今までに使った薬剤情報や特定健診情報が医師等と共有できます。
5.マイナンバーカードで医療費控除も便利に!
マイナポータルを活用して、自分の医療費情報を確認できるようになります。また、2021年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて自動入力が可能になりました。
よくある質問
Q:マイナンバーカードがないと受診ができなくなりますか
A: すべての医療機関や薬局で、今までと同じように保険証で受診することができます。なお、現在の保険証の発行については、令和6年12月2日より終了します。マイナンバーカードの取得と保険証の事前登録をお願いします。
Q:すべての医療機関・薬局で使えるようになりますか
A: マイナンバーカードで受診できるのは、オンライン資格確認を導入している医療機関や薬局に限られます。なお、令和5年4月1日より、医療機関・薬局においてシステム導入が原則として義務づけられており、順次導入を進めています。
Q:マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関や薬局は、どうすれば知ることができますか
A: 厚生労働省のホームページに、オンライン資格確認を導入している医療機関や薬局の一覧が掲載されています。また、当該医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが保険証として使えることがわかるよう、ポスター等を院内等に掲示していただくようお願いしています。
Q:マイナンバーカードを持参すれば、保険証がなくても医療機関等を受診できますか
A: オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば保険証がなくても利用できます。オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き保険証が必要です。
Q:マイナンバーカードを忘れた場合どのようにすればいいですか
A: 保険証を持参している場合は、保険証をご提示ください。保険証も持参していない場合は、現行の保険証を忘れた場合の取り扱いと同様になります。
Q:保険者が変わった場合(保険者を異動した場合)の手続きは必要ですか
A: 従来どおり保険者への異動届等の手続きは必要です。
国保の加入や喪失の手続きは、加入者ご自身で行っていただく必要がありますので、忘れずにお手続きください。
Q:窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか
A: ・被保険者証類(健康保険被保険者証/国民健康保険被保険者証/高齢受給者証)
・被保険者資格証明書
・限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証
・特定疾病療養受療証
等の持参が不要となりますが、自治体独自の医療費助成等については証類の持参が必要です。
なお、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、オンライン資格確認が導入されている医療機関では、原則として申請なしに限度額が適用されます。
保険証利用申込のお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル : 0120-95-0178
◆音声ガイダンスに従ってお進みください。
◆受付時間:平日 午前9時30分から午後8時00分
土日祝 午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)