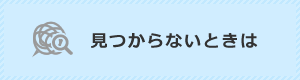ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ 五種混合予防接種
ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・Hib感染症(DPT‐IPV‐Hib)
ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・Hib感染症 五種混合(DPT‐IPV‐Hib)予防接種はジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、ヘモフィルスb型混合ワクチンを予防する予防接種です。
確実な免疫をつくるのには決められたとおりに受けることが大切ですが、万一間隔があいてしまっても初めからやり直すことはせず、規定の回数を超えないように接種します。2歳未満の百日せき患者が約半数を占めているのでなるべく早期に接種しましょう。百日せきにかかったお子様は、けんこう課までご連絡ください。
接種回数
1期初回 生後2月から生後7月に至るまでに20日以上の間隔をおいて3回
1期追加 1期初回終了後、6月から18月までの間隔で1回
(1期初回 3回接種~1期初回 追加接種まで受けて完了となります。)
対象者
生後2月から生後90月に至るまでの間にあるお子様
ジフテリア
ジフテリア菌の飛沫感染で起こります。
1981年にDPTワクチンが導入され,現在では患者発生数は年間0~1名程度ですが、ジフテリアは感染しても10%程度の人が症状が出るだけで残りの人は症状が出ないため保菌者となり、その人を通じて感染することもあります。
感染は主にのどですが鼻にも感染します。症状は高熱、のどの痛み、犬吠様の咳、嘔吐などで、偽膜を形成して窒息死することがある恐ろしい病気です。発病2~3週間後には菌の出す毒素によって心筋障がいや神経麻痺をおこすことがありますので注意が必要です。
百日せき
百日せき菌の飛沫感染で起こります。
1948年から百日せきワクチンの接種がはじまって以来、患者数は減少してきています。
百日せきは普通のカゼのような症状ではじまります。続いてせきがひどくなり,顔をまっ赤にして連続性にせき込むようになります。せきのあと急に息を吸い込むので笛を吹くような音が出ます。熱は通常出ません。乳幼児はせきで呼吸ができず、くちびるが青くなったり(チアノーゼ)やけいれんが起きることがあります。肺炎や脳症などの重い合併症をおこします。乳児では命を落とすこともあります。
破傷風
破傷風菌はヒトからヒトへ感染するのではなく、土の中にいる菌が傷口からヒトへ感染します。
傷口から菌が入り体の中で増えると菌の出す毒素のために、筋肉のけいれんを起こし、治療が遅れると死亡することもあります。患者の半数は自分では気がつかない程度の軽い傷が原因です。土の中に菌がいるため、感染する機会は常にあります。また,お母さんが免疫をもっていれば出産時に新生児が破傷風になることを防ぐことができます。
ポリオ
ポリオ(急性灰白髄炎:きゅうせいかいはくずいえん)は、「小児まひ」とも呼ばれ、ポリオウイルスが人の口の中に入って、腸の中で増えることで感染します。増えたポリオウイルスは,再び便の中に排泄され,この便を介してさらに他の人に感染します。ポリオウイルスに感染しても多くの場合、病気としての明らかな症状はあらわれずに、知らない間に免疫ができます。しかし、腸管に入ったウイルスが脊髄の一部に入り込み,主に手や足に麻痺があらわれ、その麻痺が一生残ってしまうことがあります。
日本では1960年代前半まで流行を繰り返していましたが、予防接種の効果で流行はおさまり、1980年の1例を最後に、現在まで、野生の(ワクチンによらない)ポリオウイルスによる新たな患者はありません。しかし、海外では依然としてポリオが流行している地域があり、いつ国内に入っているかわからないのでワクチン接種を続けていくことが必要です。
Hib感染症
Hib感染症は、ヘモフィルスインフルエンザ菌b型(Haemophilus influenza type b)という細菌によって発生する病気で、そのほとんどが5歳未満で発生し、特に乳幼児で発生に注意が必要です。主に気道の分泌物により感染を起こし、症状がないまま菌を保有(保菌)して日常生活を送っている子どもも多くいます。この菌が何らかのきっかけで進展すると、肺炎、敗血症、髄膜炎、化膿性の関節炎等の重篤な疾患を引き起こすことがあります。
Hibの感染による重篤な疾患として、肺炎、髄膜炎、化膿性の関節炎などが挙げられ、これらを起こした者のうち3~6%が亡くなってしまうといわれています。また、特に髄膜炎の場合は、生存した子どもの20%に難聴などの後遺症を残すといわれています。
ワクチン接種により、Hibが血液や髄液から検出されるような重篤なHib感染症にかかるリスクを95%以上減らすことができると報告されています。
副反応
臨床試験において認められた主な副反応は、接種部位の副反応として、紅斑、硬結、腫脹などがあり、接種部位以外の副反応として、発熱、気分変化、下痢、鼻水、せき、発疹、食欲減退、嘔吐などがあります。また、まれに重大な副反応として、ショック、アナフィラキシー様症状、血小板減少性紫斑病、脳症、けいれんなどがあらわれることがあります。