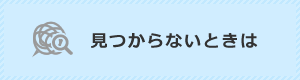菅原道真~信仰の里~
菅原道真
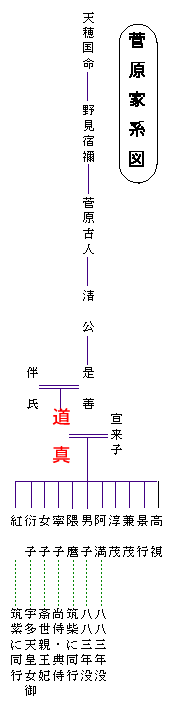 八四五(承和12)~九〇三(延喜3)。
八四五(承和12)~九〇三(延喜3)。
平安時代初期の学者,政治家。菅原氏は,もと土師氏。曽祖父古人の時,居住地(現奈良市)により菅原に改姓。従三位文章博士清公の孫,従三位参議是善の三男。
八七〇年(貞観12)方略試に合格。翌年,玄蕃助に任じ,次いで少内記に任ぜられてから官吏としての生涯が始まる。
八七七年(元慶1)文章博士。八八六年(仁和2)讃岐守となり来讃。以後,蔵人頭,参議,遺唐大使と宇多天皇に抜擢され昇進。
八九九年(昌泰2)の右大臣昇任は,律令制における門地主義からみて異例のことであった。
九〇一年(昌泰4)従二位となったが,太宰権帥に左遷され晩年は不遇であった。
讃岐守在任中,道真が民政に努めたことは『菅家文草』に散見している。
本県に滝宮天満宮をはじめ天神社が二三五社もあり,それには,いわゆる天神信仰の影響によるものもあるが,道真ゆかりの神社であることからも想像に難しくない。
死後,九九三年(正暦4)正一位太政大臣を贈られた。

信仰の里
城山神社
 888年(仁和4)五月,道真公は城山の神に祈雨の祈願をした。境内には,道真公を祀る『請雨天神』もある。請雨天神は,鼓丘の東にあったが,近い頃城山神社の傍に移した。
888年(仁和4)五月,道真公は城山の神に祈雨の祈願をした。境内には,道真公を祀る『請雨天神』もある。請雨天神は,鼓丘の東にあったが,近い頃城山神社の傍に移した。
牛ノ子山天神
菅公の松山館の跡であり,後人が祠を立てて祀った。官舎は軒が交叉しあって,海の水際に枕するように建てられていたと伝えられている。
天満天神
道真公が国司在任中に南山に遊んだとする時の南山に在り。当時の国府の正面に位置することから,「南山」と呼ぶ。菅公の旧跡から,1685年頃に藤原宅成が神霊を祀る。
黒岩天神
「いわゆる雨乞天神がこれだ」と,土地の人はいう。仁和四年,城山の神に祈雨した道真公が,この地に下って来たと伝えられ,元禄五年の干ばつの際に,創祀された。
滝宮天満宮
創建は九四八年(天暦2)二月二五日,菅原道真の怨霊を慰めるために,竜灯院綾川寺僧空澄の提唱で菅公官舎跡に一祠を建てたのが起源であるとされている。
境内西の綾川は岩石多く雨乞いに似合いの地で,竜神の影向もあったといわれており,滝宮の名はこれに由来する。名高い念仏踊は,菅公の祈雨の功をたたえたのに始まり,配所で死去した後は,菩提会念仏踊となり,毎年八月二五日に午前は滝宮神社で,午後に天満宮で行われる。