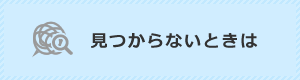坂出市デジタル郷土資料館
印刷用ページを表示する更新日:2025年5月8日更新
坂出市郷土資料館
坂出市郷土資料館は、大正時代に建築された旧坂出商業学校の校舎を活用し、昭和53年11月3日に郷土資料館として開館しました。
しかし建物強度の不足により平成25年に2階展示室、令和5年9月には1階展示室の入館を停止しています。
ここでは、これまで郷土資料館に所蔵・展示していた郷土の文化財や民俗資料について、デジタル資料館として随時公開していきます。

旧坂出商業学校校舎(現郷土資料館)
郷土資料館となっている建物は、大正8年に坂出商業学校が県立学校に昇格したときに建設された学校舎で、建設途中火災に遭いながらも、翌年に完成した建物です。大正初期の建築様式をそのままとどめており、坂出市内の学校建築として最古の建造物でもあります。
また、この地は明治以来、綾北地方の教育発祥の地でもあることから、教育振興の記念すべき建物でもあり、昭和54年11月3日には坂出市の文化財として指定された建物です。
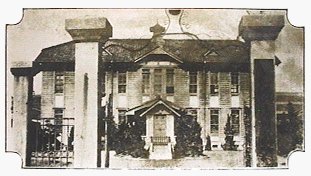
香川県立坂出商業学校本館(昭和5年)
次の写真は、昭和50年代に坂出中学校と川津中学校が合併し、坂出中学校が小山町に移転した後、郷土資料館として改装する直前のものです。

坂出市デジタル郷土資料館
|
|
|
|
|
|
|
|