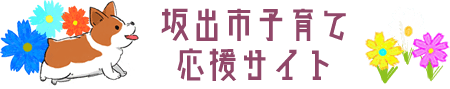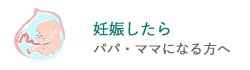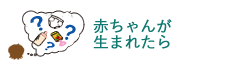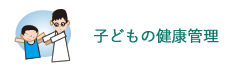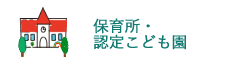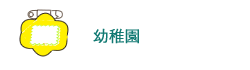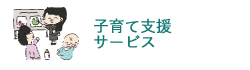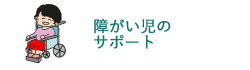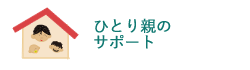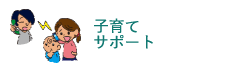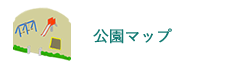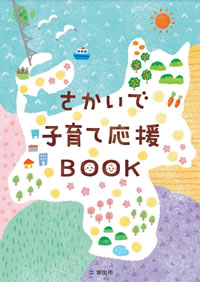児童扶養手当制度のご案内
1. 児童扶養手当制度とは
ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に貢献し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
ただし、所得制限があり、本人または同居の扶養義務者の所得により、手当の一部または全部が支給停止になる場合があります。
また、支給要件に該当しない場合は支給対象になりません。
※扶養義務者…父母、祖父母、曾祖父母、子、孫、曾孫、配偶者、兄弟姉妹
2. 児童の年齢
満18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童。ただし、児童が心身におおむね中度以上(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上)の障がいがある場合は20歳未満まで手当が受けられます。
3. 支給要件
母子家庭
次の(1)~(9)いずれかにあてはまる児童を監護している母、または養育者
(1)父母が婚姻を解消した後、父と生計を同じくしていない児童
(2)父が死亡した児童
(3)父が重度の障がいの状態にある児童
(4)父の生死が明らかでない児童
(5)父に1年以上遺棄されている児童
(6)父が母の申立てにより保護命令を受けた児童
(7)父が引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)婚姻によらないで生まれた児童
(9)棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
父子家庭
次の(1)~(9)いずれかにあてはまる児童を監護し、かつ生計を同じくしている父、または養育者
(1)父母が婚姻を解消した後、母と生計を同じくしていない児童
(2)母が死亡した児童
(3)母が重度の障がいの状態にある児童
(4)母の生死が明らかでない児童
(5)母に1年以上遺棄されている児童
(6)母が父の申立てにより保護命令を受けた児童
(7)母が引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)婚姻によらないで生まれた児童
(9)棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
次の場合は手当を受けることができません ※ [ ]は父子家庭
(1)児童が里親に委託されたり児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
(2)児童や母[父]または養育者が日本国内に住んでいないとき
(3)母[父]が婚姻しているとき(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にあるときを含む)(父[母]の障がいを事由としている場合を除く)
(4)児童が父[母]と生計を同じくしているとき
4. 就業状況の確認
受給開始から5年、または支給要件に該当した月から7年を経過したときは、就業状況等の確認が必要となり、正当な理由なく自立に向けての活動をされていない場合、手当の2分の1が支給停止対象になります。
5. 手当月額等
支払月
手当は認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、指定された受給者の銀行口座に振り込まれます。年6回(3月、5月、7月、9月、11月、1月)、支払月の前月分までが振り込まれます。ただし、その日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、その前営業日が支払日です。
なお、新規認定の事務手続きなどにより、対象者によっては支払いが遅れることがあります。
| 支給日 | 対象月 |
|---|---|
| 5月11日 | 3・4月 |
| 7月11日 | 5・6月 |
| 9月11日 | 7・8月 |
| 11月11日 | 9・10月 |
| 1月11日 | 11・12月 |
| 3月11日 | 1・2月 |
手当月額
(1)令和7年4月分から
| 対象児童 | 全部支給 | 一部支給 | 全部停止 |
|---|---|---|---|
| 1人目 | 46,690円 | 46,680円~11,010円 | 0円 |
| 2人目以降加算 | 11,030円 | 11,020円~5,520円 |
※所得により、手当の全部または一部(10円単位)が支給停止される場合があります。
※物価変動等の原因により、改定される場合があります。
手当額の見直し
毎年11月に新しい年度の所得を元に手当額の再判定をおこないます。
| 支給対象月 | 所得年度 |
|---|---|
| R6.11~R7.10 | 令和6年度(R5.1~R5.12の所得) |
| R7.11~R8.10 | 令和7年度(R6.1~R6.12の所得) |
手当額計算方法(一部支給額)
(1)令和7年4月分から
第1子手当額=46,680-(受給者の所得額 - 所得制限限度額)×0.0256619
第2子以降加算額=11,020-(受給者の所得額 - 所得制限限度額)×0.0039568
受給者の所得額
受給者の所得額
=年間収入金額 - 必要経費(給与所得控除額) - 下記の諸控除
+ 前年に受け取った養育費の8割 - 社会保険料相当額(80,000円)
所得の計算に用いる諸控除
| 控 除 額 |
※寡婦控除(一般) | 270,000円 | ※寡婦控除(特別) | 350,000円 |
|---|---|---|---|---|
| 障がい者控除 | 270,000円 | 配偶者特別控除 | 地方税法で控除された額 | |
| 特別障がい者控除 | 400,000円 | 医療費控除 | ||
| 勤労学生控除 | 270,000円 | 小規模企業共済等 掛金控除 |
※寡婦控除(一般・特別)については、受給資格者が児童の母もしくは父の場合は対象になりません。
※未婚の一人親である養育者及び扶養義務者等に限り、申請により、要件を満たす場合には寡婦(夫)控除のみなし適用を受けられる場合があります。
所得制限限度額表
所得制限の限度額は、下表に定めるとおり扶養親族等の数に応じて額が変わります。
前年もしくは前々年の所得が所得制限限度額表の額以上の方は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が支給停止になります。
扶養義務者の所得が所得制限限度額以上になると、その年度の全部が支給停止になります。扶養義務者とは、同居している受給者の父母、祖父母、曾祖父母、子、孫、曾孫、配偶者、兄弟姉妹です。
| 令和6年11月分から ※ | |||
|---|---|---|---|
| 扶養親族等の数 | 所得 | ||
| 請求者(本人) | 扶養義務者 配偶者 孤児等の養育者 |
||
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 4人以上 | 以下38万円ずつ加算 | 以下38万円ずつ加算 | 以下38万円ずつ加算 |
※ 令和6年11月分から手当の全額が受給できる場合(全部支給)の限度額、手当の一部が受給できる場合(一部支給)の限度額が引き上げられました。扶養義務者・孤児等の養育者の限度額は変更がありません。
なお、条件により上記の限度額に下記金額が加算されます。
- 請求者本人に老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合、1人につき100,000円
特定扶養親族がいる場合、1人につき150,000円 - 孤児等の養育者、配偶者および扶養義務者に老人扶養親族がいる場合、1人につき60,000円
(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く)
6.児童扶養手当と公的年金等との併給制限の見直しについて
これまで、公的年金等を受給できる場合は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月1日より、公的年金等を受給しているかたも、公的年金等の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分の手当を受給できるようになりました。詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
児童扶養手当について こども家庭庁ホームページ<外部リンク>
7. 手続き
新たに支給要件に該当するようになったかた
手当の支給を受けるためには申請が必要です。ご家庭により必要書類が異なりますので、詳しくは坂出市こども課児童福祉係(44-5027)へお問い合わせください。
なお、請求日の属する月の翌月分から支給対象となります。
また、審査や受給資格確認のために直近の支払期に間に合わない場合があります。
手当を受けているかた
受給中は、次のような届出が必要です。
- 現況届
受給資格者全員(支給停止のかたも含む)が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。
受給開始月から5年等を経過しているかたは「一部支給停止適用除外事由届出書」も提出します。 - 額改定届・請求書
対象児童に増減があったとき - 受給資格喪失届
受給資格がなくなったとき - 一部支給停止適用除外事由届出書
受給開始月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したときおよび現況届のときこの届出をしないと手当の2分の1が支給停止になる場合があります。 - その他
氏名・住所・銀行口座の変更、受給者死亡のとき
扶養義務者と同居または別居したとき、証書をなくしたとき など
- 届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになりますので、必ず手続きしてください。
- 上記のほか、受給資格の有無および額の決定のため、書類の提出が必要となる場合があります。