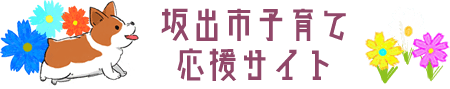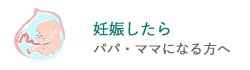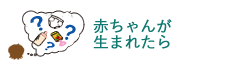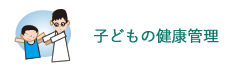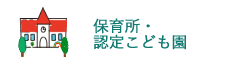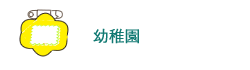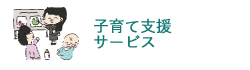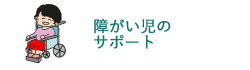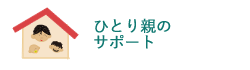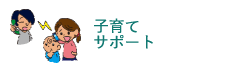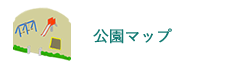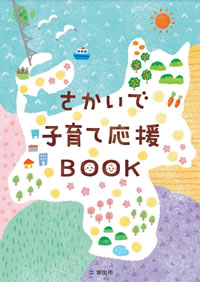令和8年度 保育施設等の入所申し込み
令和8年度 保育施設等入所の申し込み(電子申請<外部リンク>対応)
令和8年度から市内の保育施設等へ入所を希望される児童の入所申し込みを次のとおり受け付けます。(坂出市教育・保育給付支給認定申請書 兼現況届 兼保育施設等入所申込書は、11月からお近くの保育施設等またはこども課保育幼稚園係で配布予定です。)
入所申し込み案内をよくご確認のうえ、手続してください。
令和8年度保育施設等入所申し込みのしおり1 [PDFファイル/736KB]
令和8年度保育施設等入所申し込みのしおり2【記入例】 [PDFファイル/1.01MB]
令和8年度保育施設等入所申し込みのしおり3【市内保育施設配置図】[PDFファイル/685KB]
★★重要★★ 令和8年度から提出する書類などに変更があります
- 今年度から重要事項確認書兼同意書の提出が必要になりました。
- 「基本の申込書類(「保育施設等入所申込書」及び「重要事項確認書兼同意書」)」に不備がある場合、受付ができません。必ず期限に余裕をもって 申請してください。
- 自営業のかたにおける「保育が必要なことを証明する書類」について、就労証明書だけでなく、直近の確定申告書(屋号の記載有り)の写しも提出してください。(開業からの日数が少ないなどの理由により、提出が不可能なかたについては、こども課までご相談ください。他の書類をご提出いただきます。)
- 保護者が求職中の場合、入所後3 か月以内に就労証明書を提出していただきます。3か月以内で就労先が決まらない場合、「求職活動」の認定期間の延長は 1 回のみ可能です。(延長時には求職活動状況を報告していただきます。継続的な活動を確認できなければ、延長できない場合があります。)入所後 6 か月以内に就労先が決定せず、継続利用を希望する場合、再度入所申込書を提出していただき、入所再選考となります。園の空き状況によっては、通い続けることができない場合がありますので、ご承知おきください。
入所資格
市内に住所を有する小学校就学前の乳幼児で、保育が必要な児童。
- 公立保育所・公立認定こども園は、1歳以上児。(南部保育所のみ生後6か月以上児。)
- 私立保育所・事業所内保育所は、生後8週間以上児。
- 私立認定こども園の2号認定は満3歳以上児、3号認定は生後8週間以上満3歳未満児。(ただし、ルンビニ幼稚園は満2歳後の次の4月からの入所となります。)
「保育が必要な児童」とは?
児童の保護者のいずれもが、次の各号のいずれかに該当することにより児童を保育することができないと認められる場合。
- 両親とも仕事をしていること。(就労時間:64時間/月 以上)
- 妊娠中または出産後間がないこと。
- 疾病にかかっている、負傷している、精神や身体に障がいを有していること。
- 同居の親族を常時介護していること。
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
- 求職活動をしていること。
- 就学していること。
- 虐待やDVのおそれがあること。
- 育児休業取得時に、既に保育所を利用しているこどもがいて継続利用が必要であること。
- 上記のいずれかに類する状態にあること。
保護者が求職中の場合、入所後3か月以内に就労証明書を提出していただきます。3か月以内で就労先が決まらない場合、「求職活動」の認定期間の延長は 1 回のみ可能です。
育児休業から復帰されるかたは、仕事復帰月の2か月前から保育の実施を希望できます。
受付期間
- 各保育施設等での申し込み
受付期間 令和7年11月10日(月曜日)~11月21日(金曜日)
※土曜日・日曜日を除く
※私立施設での受付期間・各施設での受付時間は各施設にお問い合わせください。
- 市役所こども課での申し込み
受付期間 令和7年12月8日(月曜日)~12月12日(金曜日)午前9時~午後5時
- 入所の申し込みは、児童の出生前から行うことができます。
- 既に入所している場合や令和7年度の申し込みをしている場合でも、令和8年4月以降も引き続き入所を希望する場合は、申し込みが必要です。
- 新規入所の児童については、入所後2週間から1か月程度の慣らし保育の期間があります。
- 入所日は毎月1日となります。月途中からの入所は実施しておりません。
- 認定こども園1号を希望されるかたについては、直接園にお問い合わせください。
上記期間内に申し込みできなかった場合
- 4月入所を希望する場合、市こども課までお申し込みください。ただし、令和8年1月30日(金曜日)を過ぎると5月以降の利用調整の対象となります。
-
年度途中(5月以降)からの入所を希望する場合、入所希望月の前々月末日(土曜日・日曜日・祝日の場合はその前日)までに市こども課までお申し込みください。
申し込み方法
「坂出市教育・保育給付支給認定申請書 兼現況届 兼保育施設等入所申込書」に必要な事項を記入し、添付書類を添えて提出してください。
○提出書類
●坂出市教育・保育給付支給認定申請書 兼現況届 兼保育施設等入所申込書
坂出市教育・保育給付支給認定申請書 兼現況届 兼保育施設等入所申込書 [PDFファイル/841KB]
坂出市教育・保育給付支給認定申請書 兼現況届 兼保育施設等入所申込書 [Excelファイル/49KB]
●重要事項確認書兼同意書
(印刷する場合は両面印刷してください。)
○添付書類
|
(1)保育を必要と証する書類(保育認定のための資料)※父母それぞれ1枚 |
|
|---|---|
|
(1)就労 |
●就労証明書 ※自営業の場合は、確定申告書の写しの提出が必要となります。(開業からの日数が少ないなどの理由により、提出が不可能なかたについては、こども課までご相談ください。他の書類をご提出いただきます。) |
|
(2)妊娠・出産 |
●母子健康手帳の写し(表紙及び出産予定日等記載のページ) |
|
(3)疾病・障がい |
●医師の診断書(市の様式。保護者が保育できないとわかる内容のもの)または、障がいを有していることを証する書類(障がい者手帳の写し等) |
|
(4)介護・看護 |
●医師の診断書(市の様式。保護者が保育できないとわかる内容のもの) |
|
(5)災害復旧 |
●罹災証明書等 |
|
(6)求職活動 |
●申出書またはハローワーク登録証の写しまたは不採用通知書等 |
|
(7)就学 |
●在学証明書 ●授業スケジュール等(修了予定日がわかるもの) ●時間割等の写し(授業時間がわかるもの) |
|
(8)虐待・DV |
●事実を証明できる書類 |
|
(9)育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要 |
●産休・育休期間の記載がある就労証明書 |
|
(2)その他(該当する場合のみ提出して下さい。) |
|
|
入所児童が第3子以降である場合 |
●保育施設等児童世帯内容申請書 |
|
入所児童が第2子で、兄・姉が坂出市の認定を受けずに国立幼稚園や新制度未移行幼稚園、認可外保育所等に通う場合 |
●幼稚園等の在籍証明書(兄・姉のもの) |
|
令和7年1月1日または令和8年1月1日に坂出市に住民登録がない場合 |
「坂出市教育・保育給付支給認定申請書兼現況届兼保育施設等入所申込書」に個人番号(マイナンバー)を記載の上、個人番号確認書類と身元確認書類をお持ちください。個人番号(マイナンバー)申告について [PDFファイル/308KB] |
- その他状況に応じて必要な書類を提出していただくことがあります。
- 添付書類の記載内容について、必要に応じて関係機関へ問い合わせる場合がありますのでご了承下さい。
- 必要書類が揃わない場合、施設利用承諾を取り消す場合があります。
- 一度提出していただいた書類は返却できません。あらかじめコピーをしておいてください。
- やむを得ず申し込み時に添付できない場合は、令和7年12月26日(金曜日)までに提出してください。ご連絡なくこの期日に間に合わない場合、書類不備としての入所選考となりますのでご了承ください。
併願について
保育施設等(2・3号認定)と幼稚園等(1号認定)を併願する場合、(2・3号認定用)と(1号認定用)で申込書を2枚提出していただく必要があります。
2・3号認定用は申請書のおもて面『保育の希望の有無』について、一番上の「有」と中央の「有(併願)」の2か所に☑し両面に必要事項を記入、1号認定用は一番下の「無」と中央の「有(併願)」の2か所に☑しおもて面の必要な部分のみ記入し、それぞれの受付場所に申請してください。
どちらに入所するか決定した時点で、一方の支給認定申請を取り下げてください。
入所が決定した施設(認定区分)に応じた支給認定証を発行いたします。
利用調整・入所の承諾
- 保育施設等の入所者数(入所希望者数)や、職員数等の状況により、利用申し込みをしても保育施設等へ入所できない場合があります。
- 利用調整の結果は、入所月の前月の15日頃に施設利用承諾通知書または施設利用保留通知書により、保護者へ通知いたします。
- 4月入所については認定事務が集中するために審査に時間を要することから、2月末頃に通知いたします。
- 施設利用保留通知書は、当初の入所希望月のみ発送いたします。
- 当初の入所希望月以降は、入所が決定した場合にのみ、施設利用承諾通知書を発送いたします。
認定区分
- 1号認定(教育標準時間認定)
児童が満3歳以上で教育を希望する場合(幼稚園・認定こども園1号)
- 2号認定(満3歳以上・保育認定)
児童が満3歳以上で保護者の就労等により保育が必要な場合(保育所・認定こども園2号)
- 3号認定(満3歳未満・保育認定)
児童が満3歳未満で保護者の就労等により保育が必要な場合(保育所・事業所内保育所・認定こども園3号)
保育必要量(保育時間)
- 保育標準時間(最長11時間)
公立保育所・公立認定こども園 7時30分~18時00分
- 保育短時間(最長8時間)
公立保育所・公立認定こども園 8時30分~16時30分
※私立施設については、直接園へお問い合わせください。
※実際の預かり時間は、お子様の年齢や発達状況、ご家庭の環境(保護者の就労時間等)などにより、保育必要量の範囲内で変更する場合もあります。
保育料
令和8年4月1日現在の年齢と両親等の市民税額の合計で保育料を決定します。
- 新年度4月から8月までの保育料→前年度市民税額により算定
(前々年1月から12月までの収入から算定された市民税所得割額等)
- 新年度9月から翌3月までの保育料→当年度市民税額により算定
(前年1月から12月までの収入から算定された市民税所得割額等)
令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が始まり、3歳から5歳児までの子ども及び0歳から2歳児の非課税世帯の子どもの利用料が無償となります。
なお、保育料に含まれていた副食費や行事費等の実費負担分については無償化の対象外となり、引き続き保護者の皆さんのご負担となります。
その他
次のような場合は市こども課までお問い合わせください。
- 申込書に記載した内容(住所、世帯状況、保育を必要とする理由等)に変更があった。
→支給認定変更などの手続きが必要です。 - 提出した就労証明書の内容に変更(勤務先が変わった、退職した等)があった。
→就労証明書の再提出や、支給認定変更などの手続きが必要です。 - 保育必要量(保育時間)や保育期間を変更したい。
- 保育料・副食費の引落し口座を変更したい。(私立認定こども園・事業所内保育所の保育料、私立保育所・私立認定こども園の3歳から5歳児までの副食費の納付方法は施設へ直接お問い合わせください。)
マイナンバーカードを利用した電子申請が利用できます
保育施設等の利用に必要な認定申請や入所申込の手続について、マイナンバーカードによる公的個人認証を利用し、電子申請を行うことができるようになりました。 電子申請ページはこちらへ(外部サイトへリンク)<外部リンク>
- 申請にあたっては、マイナンバーカードと添付書類の準備が必要です。
- 電子申請が可能な手続きの中には、官公署から発行された証明書等の原本の提出が必要な手続きがあります。その提出があるまで申請が完成しませんので、ご注意ください。
- 電子申請において必要書類の画像が添付されていない場合、または、画像が不鮮明である場合は、この書類のコピー等を提出するよう求めることがあります。